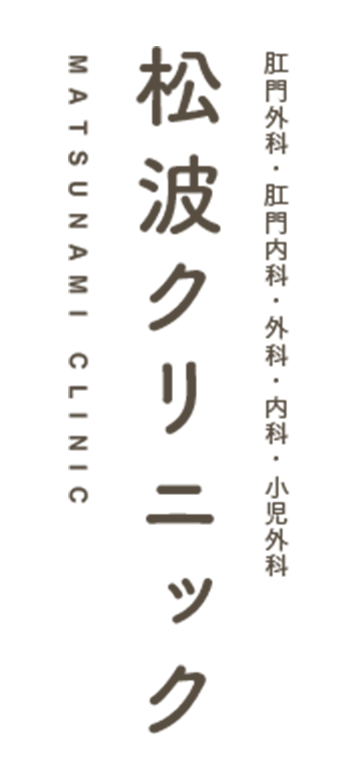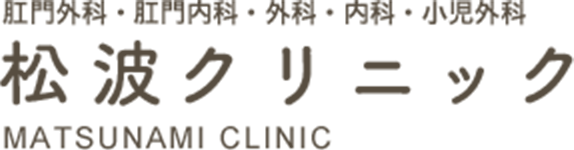【新潟】産後にいぼ痔になりやすい理由と対処法
産後いぼ痔でお悩み?出産後になりやすい理由と対策を肛門科医が解説!
産後にいぼ痔が発症しやすい理由は、妊娠中の体重増加や出産時のいきみ、ホルモンバランスの変化による便秘などが挙げられます。新潟でいぼ痔にお悩みの方は、松波クリニックまでご相談ください。
産後はできやすい?出産後にいぼ痔が発症しやすい理由

いぼ痔は、肛門粘膜の下にある直腸静脈叢と呼ばれる血管が張り出してできるものです。以下に、産後にいぼ痔ができやすい主な理由をご紹介します。
妊娠中の体重増加による肛門への負担
妊娠中の体重増加は避けられません。平均すると妊娠前の体重から8~12kgほど増加するのが一般的です。お腹の赤ちゃんや子宮の増大、母体の貯蔵脂肪・体液によって体重が増加し、増えた体重は肛門周りの血管に負担をかけます。妊娠中は徐々に子宮が大きくなり、直腸周りの血管を圧迫するためです。その結果、うっ血が起こり、便秘などの症状が現れやすくなります。便秘は、さらなるいぼ痔の発症リスクにもなるため注意が必要です。
出産時の肛門周囲の怪我や裂傷
産後にいぼ痔になりやすい理由の一つに「出産時の肛門周囲の怪我や裂傷」があります。分娩時のいきみには、通常の排便時の何倍もの力がかかります。この強いいきみによって肛門周囲に裂傷や怪我ができ、いぼ痔ができやすくなるのです。
特に、お産が長引いた場合は、いきみの回数も多くなり、肛門周囲への負担が大きくなります。また、吸引分娩や鉗子分娩では、直接肛門周囲を押す力が加わるため、怪我や裂傷のリスクが高まります。
こうした出産時の怪我や裂傷は、血管の損傷を招き、うっ血を引き起こします。うっ血が続くと、いぼ痔につながるのです。出産時のいきみには通常の排便時よりも大きな力がかかるため、肛門周囲に怪我や裂傷ができやすく、これがいぼ痔発症の一因となります。
便秘が続きやすい
産後は以下の理由から便秘になりやすくなります。
ホルモンバランスの変化
分娩後は妊娠中に多く分泌されていたホルモン(プロゲステロン)が急激に減少します。このホルモンは腸の蠕動運動を低下させる働きがあるため、その減少が便秘の一因です。
運動不足
産後は体の回復に専念する期間が続くため、外出する機会が減り運動不足になりがちです。運動不足は腸の動きを鈍くさせ、便秘の一因となります。
授乳による脱水
授乳中は母乳の分泌に伴い体内の水分が奪われるため、脱水状態になりやすくなります。水分不足は便の硬結を招き、便秘の原因にもなります。
便秘が続くと、いきみが多くなり肛門周りへの負担が増えます。産後のお母さんはいぼ痔になりやすい状態ですので、便秘対策を積極的に心がけましょう。
産後のいぼ痔の対処法

生活習慣の改善(食事、運動など)
いぼ痔の症状を和らげるためには、生活習慣を見直すことが大切です。
長時間座りっぱなしは避け、1時間に1回程度は軽い運動や動作を心がけてください。また、アルコール類や香辛料などの刺激物は肛門を刺激するため、控えめにしましょう。食物繊維の多い食品を意識的に取り入れることで、便秘の予防にもなります。
授乳中は特に水分補給が重要です。1日に1.5L以上の水分補給を心がけましょう。
このように、いぼ痔の改善には食事と適度な運動が欠かせません。生活習慣の見直しから始めましょう。
坐薬や軟膏による自己ケア
いぼ痔の初期症状に対しては、坐薬や軟膏による自己ケアが有効です。坐薬は肛門に直接挿入し、軟膏は患部に直接塗布します。これらにはうっ血や腫れを改善する効果があり、症状の軽減が期待できます。坐薬や軟膏は、痔の症状が軽度の場合に自己で行える対処法です。症状が改善しない場合や悪化した場合は、早めに医師に相談することが重要です。
病院受診が必要な場合
いぼ痔の自覚症状があり、下記のような場合は、早めに病院で診てもらうことをおすすめします。
- 痛みや出血が続く
- 飛び出したいぼ痔が中に戻らない
- いぼ痔以外の病気(直腸脱、直腸・肛門ポリープなど)の可能性がある
特に出血量が多く、立ちくらみや息切れ、疲労感、青白い顔色など貧血の症状がある場合は注意が必要です。
無理に押し込もうとしてもいぼ痔は戻らず、かえってひどくなるおそれがあります。いぼ痔が大きくなると、肛門からの出血量も増え、貧血につながるため、自己判断せず専門医に相談しましょう。
いぼ痔の予防策
妊娠中からの便秘対策
妊娠中は、ホルモンの変化や子宮の圧迫などによって便秘になりやすくなります。便秘は、いぼ痔の原因になるため予防策を立てることが重要です。具体的には以下のような予防策があります。
- 野菜や果物、全粒穀物など食物繊維を意識的に摂取する
- 1.5リットル以上/1日の水分補給
- 腹部マッサージや運動を取り入れる
- 便意を感じたらすぐにトイレに行く習慣をつける
妊娠中から上記の予防法を実践することで、出産後のいぼ痔の発症リスクを下げられます。
出産時の怪我を最小限に
出産時の過度ないきみや子宮口の拡張は、肛門周囲に裂傷や怪我を引き起こす可能性があります。そのため、出産に際しては以下のようなポイントを心がけることが重要です。
- 適切な呼吸法を身につける
- 無理なくゆっくりと息を吐く
- お産の進行に合わせて医療スタッフの指示に従う
産後の血行促進
冷えは血行を悪くし、いぼ痔を悪化させる原因となります。そのため、温かいお風呂に入って血行を促進させるようにしましょう。体を温め、肛門周囲の血流改善に役立ちます。
また、適度な運動も血行促進に効果的です。運動は腸の動きを活発にし、同時に肛門周囲の血行も促進されます。軽い散歩程度の運動から、ストレッチ体操やジョギングなど徐々にペースを上げていきましょう。
ただし、無理な運動は控えめにしてください。血行過剰を招き、かえっていぼ痔を悪化させるおそれがあります。
出産後のいぼ痔にお悩みなら新潟の松波クリニックへ
産後は、妊娠中の体重増加や出産時のいきみ、ホルモンバランスの変化による便秘など体内の変化からいぼ痔ができやすくなりますが、産後のいぼ痔で悩む必要はありません。適切な対処と予防策でトラブルを最小限に抑えることができます。生活習慣の改善や便秘対策などを実践し、いぼ痔の発症や再発を防ぎましょう。
継続的な出血や痛み、中に戻りにくくなった場合は医療機関を受診し、いぼ痔の悪化を防ぐ必要があります。自己判断せずに速やかに肛門科の専門医に相談しましょう。医療機関での診療を受けることで、専門医の助言に基づいた適切な治療法を選択することができます。
新潟の松波クリニックでは、肛門外科・肛門内科をはじめ、外科・内科・小児外科に対応しております。出産時のいきみや妊娠によるホルモンバランスの変化などにより、産後は便秘になりやすい状態です。特に授乳中は、水分が母乳となって出て行くため水分不足に陥りやすくなり、便秘から痔になってしまうことも少なくありません。肛門外科・肛門内科の担当医として、いぼ痔などおしりにお悩みをお持ちの方には専門的な治療も行っております。新潟で便秘や痔の症状にお悩みの方は、松波クリニックまでお気軽にご相談ください。
肛門外科・内科のいぼ痔や切れ痔治療に関するコラム
- 【新潟の肛門外科医院】肛門疾患である痔核と裂肛はどんな症状?
- 予約不要!新潟の肛門外科が便秘の原因と二次障害と医療機関の選び方を解説
- 【新潟の肛門外科】入院は必須?肛門がんの概要や過敏性腸症候群の特徴と排便障害のケア
- 新潟の医院・肛門内科から便秘でお悩みの方へ!肛門内視鏡検査の必要性
- 新潟の肛門内科で診療!おしりのトラブルで女性も安心の受診ガイド
- 新潟の肛門内科専門医に聞く!便秘・下痢の悩み解決法とは
- 新潟でいぼ痔治療!腫れを和らげる生活習慣の改善策と適切な治し方
- 【新潟】産後にいぼ痔になりやすい理由と対処法
- 【新潟】切れ痔が悪化する前に治療を!自宅での予防策と正しい緩和ケア
- 【新潟】切れ痔か大腸がんかは検査が必要!初期症状から見分ける方法