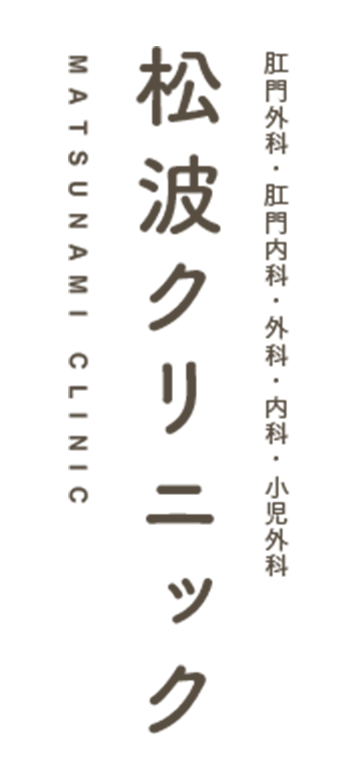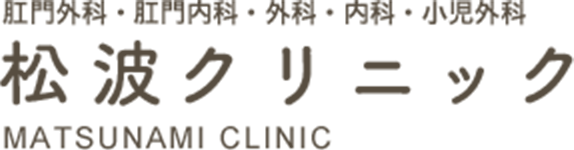【新潟】切れ痔の悪化を防ぐには?排便習慣とトイレのコツ
【新潟】切れ痔の原因とは?正しいトイレの使い方や排便指導の内容などを解説
切れ痔は、排便時の痛みや出血を伴うつらい症状です。こちらでは、排便時に切れ痔が悪化しないためのトイレ習慣のコツ、便通を良くする方法、専門家による排便指導や治療について解説いたします。新潟周辺でおしりの悩み・心配事があるときは、正しい知識と習慣を身につけて、症状の悪化を防ぎましょう。
切れ痔は排便習慣の乱れが原因?

切れ痔の多くは、硬い便の排出や強いいきみ、排便時間の長さといった排便習慣の乱れが深く関係しています。これらが重なると肛門に過度な負担がかかり、皮膚が裂けてしまうのです。
硬便が肛門に与える影響
排出時に肛門の皮膚や粘膜に強い摩擦が生じます。特に便秘によって便が長く腸内にとどまると、水分が吸収されてさらに硬くなります。これを無理に出そうとすると、肛門が裂けて切れ痔を起こすことがあります。切れ痔の傷は小さくても、排便のたびに刺激を受けて治りにくく、慢性化することもあります。
過度ないきみが引き起こす問題
排便時のいきみは必要な動作ですが、力みすぎると肛門への負担が大きくなります。特に硬便の場合、強くいきむことで肛門周囲の血管がうっ血し、筋肉が過度に緊張します。その結果、血行が悪化し、炎症や裂傷が悪化することがあります。また、圧力がかかることで傷が広がるリスクも高まります。
長時間の排便が切れ痔を悪化させる理由
トイレでスマートフォンを見たり、本を読んだりする習慣はありませんか。このような習慣は座る時間が長くなり、肛門に重力がかかってうっ血しやすくなります。これが切れ痔の治癒を遅らせ、新たな傷や炎症を招くこともあります。また、長時間の座位は余計ないきみを引き起こしやすく、結果的に肛門への負担を増すことになります。排便は3分以内で済ませるのが理想的です。
排便習慣の乱れを見直すことは、切れ痔の予防や悪化の防止に欠かせません。まずは日々の排便のタイミングや姿勢、時間などを意識してみましょう。
正しいトイレの使い方と便通改善のヒント

切れ痔の悪化を防ぐためには、排便時の姿勢や力の入れ方、そして便通を整える生活習慣が大切です。
正しいトイレの使い方
排便時のちょっとした工夫が、肛門への負担を軽くし、切れ痔の悪化を防ぐことにつながります。
前かがみになる姿勢
便座に座ったときは、少し前かがみになるよう意識してみてください。背筋を伸ばしすぎず、膝をやや立てる姿勢が、便をスムーズに出す助けになります。和式トイレの体勢に近いイメージです。足元に台を置いて膝を高くするのもおすすめです。
いきむタイミングと力の入れ方
自然な便意を感じてからいきむようにし、まだ便意がないうちから無理にいきむのは避けましょう。力を入れるときは息を吐きながら、お腹にゆっくりと力を込めるようなイメージです。急に強くいきむと肛門に負担がかかります。
排便時間を長引かせない
トイレに座る時間は3分以内を目安にしましょう。便が出なくても、長く座り続けずにいったん切り上げ、再び便意を感じたときに改めて行くようにしてください。スマートフォンや雑誌などの持ち込みは、トイレの滞在時間を長引かせる要因になります。
ウォシュレットの使い方に注意
ウォシュレットは肛門を清潔に保つのに便利ですが、使い方次第では刺激になってしまうことがあります。水圧は弱めに設定し、温水を使いましょう。ノズルを肛門に近づけすぎないように注意し、洗浄後は柔らかいトイレットペーパーでやさしく水分を拭き取ります。
便通をよくするための食生活と生活習慣
便通が整えば、硬い便による肛門への刺激が減り、切れ痔の症状を抑えやすくなります。
こまめな水分補給
便の水分量を保つため、1日1.5~2リットルを目安に水分をこまめに摂取しましょう。特に起床時にコップ1杯の水を飲むと、腸が動きやすくなります。
食物繊維をバランスよく摂る
食物繊維は便のかさを増やし、やわらかくする働きがあります。わかめや果物などの水溶性食物繊維と、野菜やきのこ類などの不溶性食物繊維を偏りなく取り入れるのがポイントです。片方に偏りすぎると、かえって便秘を悪化させることがあります。
規則的な食事
毎日決まった時間に食事をとることで、腸の動きが安定しやすくなります。特に朝食は腸の活動を促すうえでも大切です。
軽い運動を取り入れる
ウォーキングやストレッチなど、無理なく続けられる運動は腸の動きを助け、血流の改善にもつながります。
ストレス管理
ストレスは自律神経のバランスを崩し、便秘や下痢につながることがあります。趣味の時間をとる、リラックスできる環境を整えるなど、自分に合った方法でストレスを和らげましょう。
便意を我慢しない
便意を感じたら、できるだけ早めにトイレに行く習慣をつけましょう。我慢しているうちに便が硬くなり、肛門への刺激が強くなってしまいます。
日常の中でこうした工夫を少しずつ取り入れていくことで、便通の改善が期待でき、切れ痔による悩みの軽減につながります。
切れ痔が治りにくいときの排便指導・治療の流れ
セルフケアで改善が見られない場合や症状が重いときは、肛門外科の受診が重要です。肛門外科では、痔の治療だけでなく、排便習慣の改善に向けた指導も行われています。
肛門外科受診の重要性
切れ痔を放置すると、慢性化して潰瘍ができたり、肛門が狭くなる「肛門狭窄」を引き起こすことがあります。また、出血が痔以外の病気による可能性もゼロではありません。自己判断に頼らず、医師に相談することが大切です。医師による診察では、正確な診断のもとで適切な治療と排便指導が受けられます。
診察と排便習慣のヒアリング
初診では、まず問診が行われます。症状(痛み・出血の有無や程度)、排便の状態(便の硬さ・回数・いきみの有無・排便時間)、過去の病歴や生活習慣などが詳しく聞かれます。このとき、自分の排便習慣を正直に伝えることが、適切な指導につながります。恥ずかしさを感じるかもしれませんが、普段のトイレでの様子や食生活について率直に話しましょう。
その後、視診や触診などが行われます。痛みを伴いやすい切れ痔の診察では、できる限り負担を減らすよう配慮されています。
具体的な排便指導の内容
排便指導は個々の症状に応じて行われますが、一般的には以下のような項目が含まれます。
- 便秘・下痢の改善指導
- 排便時の正しい姿勢
- いきみ方の工夫
- トイレ滞在時間の調整
- 温めることの重要性
- 排便日記の活用
薬物療法と手術療法
排便指導とあわせて、症状に応じて薬や手術による治療が検討されます。
薬物療法
炎症や痛みを抑えるために、軟膏や坐薬などの外用薬が処方されます。便をやわらかくするために、内服薬が出されることもあります。
手術療法
薬や生活改善で効果が見られない場合や、肛門狭窄が進んでいる場合には、手術が選択肢になります。手術の方法は症状によって異なり、肛門を広げる処置や、傷を修復するものなどがあります。最近では、身体への負担が少なく回復が早い手術法も増えています。
肛門外科で行われる排便指導や治療は、切れ痔の根本的な解決と再発予防のためにも有効です。つらい症状を我慢し続ける前に、まずはご相談ください。
切れ痔の悩みを相談するなら新潟の松波クリニックへ
痔の症状があっても、「恥ずかしい」「そのうち治るかも」と思い、我慢してしまう方は少なくありません。しかし、適切な治療を受けずにいると症状が進行したり、痔ではなく別の病気だったというケースも見られます。早期に対処し、悩みを解消しましょう。
新潟の松波クリニックでは、おしりに関する悩み・心配事の解決をお手伝いしております。痔をはじめ、気になることがありましたら、まずはご相談ください。
【新潟】肛門外科・内科治療、いぼ痔や切れ痔に役立つコラム
- 【新潟】肛門が痒い原因とは?市販薬使用時の注意点や肛門外科受診の重要性
- 【新潟】肛門の痛みの原因・放置するリスク・肛門外科の診察内容
- 【新潟】肛門から出血を引き起こす疾患や肛門外科受診の目安について
- 【新潟】肛門内科の受診は恥ずかしい?配慮のポイントと早期受診のメリット
- 【新潟】肛門内科で対応する症状や診察の流れ・検査内容とは?
- 【新潟 肛門内科】便秘の特徴・生活習慣の見直しポイント・排便習慣の作り方
- 【新潟】いぼ痔の悪化を防ぐ!座り方と日常生活でできる予防法
- 【新潟】いぼ痔の進行段階や症状を悪化させるNG習慣とは?
- 【新潟】切れ痔の放置は危険信号!悪化・再発を防ぐための対処法
- 【新潟】切れ痔の悪化を防ぐには?排便習慣とトイレのコツ