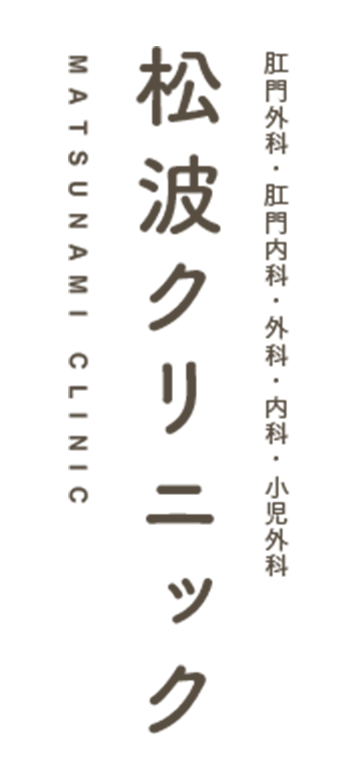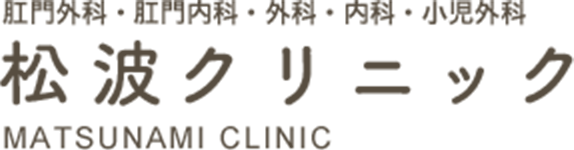【新潟】肛門から出血を引き起こす疾患や肛門外科受診の目安について
【新潟】肛門からの出血…考えられる疾患は?肛門外科受診の目安や診療の流れ・治療なども解説
肛門からの出血に気づくと、痔なのか、それとも他の病気が隠れているのか、判断に迷うことも少なくありません。出血の色や量、出るタイミングなどによって、おおよその傾向を把握できますが、正確な診断には医療機関の受診が不可欠です。こちらでは、出血の特徴から考えられる原因、受診の目安、肛門外科での診療内容などについて、ご紹介します。新潟周辺で肛門のトラブルを解決したい方は、参考にしていただければと思います。
肛門からの出血で考えられる疾患とは?

排便後の出血と聞くと、まず痔を思い浮かべるのではないでしょうか。実は、痔以外にもさまざまな疾患が出血の原因となっていることがあります。
痔
痔には主に3つのタイプがあります。いぼ痔(痔核)は肛門周囲の血管がうっ血してできるもので、内痔核と外痔核に分類されます。内痔核は痛みが少ないものの、排便時に鮮血が見られます。
切れ痔(裂肛)は、硬い便などで肛門の皮膚が切れて出血するもので、強い痛みを伴います。出血量は少なく、紙や便にわずかに付着する程度ですが、便秘との悪循環を招きやすい点に注意が必要です。
痔瘻(あな痔)は、細菌感染によって肛門周囲に膿の通り道ができる痔です。常に膿が出るのが主な症状で、血が混じることもあります。
大腸ポリープ・大腸がん
大腸ポリープや大腸がんは、初期段階では自覚症状がないことが多いものの、進行すると出血が見られることがあります。早期発見・早期治療が非常に重要です。便に血が混じっていたり、赤黒い出血が続いたりする場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患は、腸の粘膜に炎症が起こる病気です。これらの病気では、粘液が混じった血便や、下痢と出血が同時に起こることがあります。腹痛や発熱、体重減少などの全身症状を伴うことも少なくありません。慢性的な炎症が続くため、適切な治療が必要です。
憩室出血
大腸の壁にできた小さな袋状のへこみ(憩室)からの出血です。痛みがないことが多いものの、突然大量の鮮血が出るのが特徴です。出血量が多い場合は、貧血やめまいなどを引き起こす可能性があります。
虚血性腸炎
大腸への血流が悪くなることで炎症が起こる病気です。突然の強い腹痛とともに、下痢や血便が見られます。高齢者に多く見られますが、若い世代にも起こり得ます。
感染性腸炎
細菌やウイルスなどの感染が原因で起こる腸炎です。激しい下痢や腹痛とともに、血便が見られることがあります。発熱や吐き気、嘔吐などを伴うこともあります。
出血の量や色、痛みの有無だけでは、完全に原因を見分けるのは困難です。そのため、疑わしい症状が続くときは、肛門外科の受診をご検討ください。
排便後の出血の色・量から見える原因と受診の目安

排便後に出血があった場合、色や量、排便時の状況などを観察することがポイントです。
出血の色と量からわかる原因の傾向
肛門からの出血は、色によっても異なります。
鮮やかな赤い血(鮮血)の場合
肛門に近い場所からの出血は、血液が空気に触れる時間が短く、鮮やかな赤色をしています。便の表面に付着したり、ポタポタと垂れたり、拭いた紙に付いたりします。これらは痔が原因の可能性が高いでしょう。しかし、大量の鮮血が突然出た場合は、憩室出血や大腸ポリープ・大腸がんも考えられます。特に、痛みがないのに大量の出血がある場合は、注意が必要です。
暗赤色や黒っぽい血(タール便)の場合
胃や十二指腸、小腸など、消化管の上部からの出血が疑われる場合は、暗赤色や黒っぽい色(タール便)が見られます。タール便とは、ベタベタとした黒い便で、胃や十二指腸からの出血(消化性潰瘍など)が考えられます。少量でも持続的に出血が続いている場合は注意が必要です。
粘液が混じった血便の場合
血液とともに粘液が混じっている場合は、炎症性腸疾患や感染性腸炎の可能性が考えられます。これらの疾患は、腸の粘膜に炎症が起こることで粘液が増え、出血を伴います。下痢や腹痛、発熱などの症状を伴うことが多いです。
受診のタイミングと見過ごしてはいけない症状
以下のような症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。中には緊急対応が必要なものもあります。
- 出血量が非常に多い(便器が真っ赤になる、下着を汚すなど)
- めまい、立ちくらみ、顔面蒼白など、貧血症状がある
- 出血に加えて、腹痛、吐き気、発熱などの全身症状がある
- 便が黒っぽい(タール便)
- 出血が止まらない、または繰り返す
- 意識が朦朧とする
- 鮮血が何日も続く
- 便秘や下痢を繰り返す、便が細くなるなど、排便パターンに変化が見られる
- 体重減少や食欲不振が見られる
- 血便に粘液や膿が混じる
- 市販薬で改善しない
大量出血や貧血症状がある場合は、救急外来の受診も視野に入れてください。
肛門外科では何をする?診察内容と治療の進め方
肛門からの出血で肛門外科を受診した場合、どのような診断が行われ、どのような治療法が選択されるのでしょうか。不安なく診察を受けられるよう、一般的な流れと治療の選択肢について解説します。
診察の流れ
肛門外科を受診すると、まずは問診が行われます。いつから出血があるのか、出血の色や量、排便時の痛み、その他の症状の有無、既往歴などを詳しく確認します。正直に伝えることが正確な診断につながります。
視診・触診
視診では、肛門周辺の皮膚の状態、痔核の有無などを目視で確認します。触診では、医師が肛門に指を挿入して、直腸内の状態や痔核の硬さ、腫れなどを確認します。少し抵抗があるかもしれませんが、痛みはほとんどありません。
肛門鏡検査
肛門鏡検査は、肛門内部を直接観察するための器具を用いた検査です。肛門鏡を使用することで、内痔核や切れ痔、直腸の粘膜の状態などを詳細に確認できます。この検査も通常、大きな痛みはありません。
必要に応じた精密検査
痔以外の疾患が疑われる場合や出血が続く場合は、さらに精密な検査が必要になることがあります。例えば、大腸内視鏡検査は大腸全体を詳しく観察する検査で、大腸ポリープや大腸がん、炎症性腸疾患などの発見に有効です。出血の原因が痔以外、他の消化器症状がある場合に推奨されます。便潜血検査は、目に見えない血液が便に混じっていないかを確認する検査です。血液検査では、貧血の有無や炎症反応などを調べます。
患者様の症状を総合的に判断したうえで、必要な検査を提案します。
肛門外科での治療法
診断結果を踏まえて、保存的治療や手術治療が選択されます。
保存的治療
初期の痔や軽度の場合は、手術をせずに症状の改善を目指す保存的治療が中心です。
生活習慣の改善では、便秘の解消、排便時間の短縮、長時間の座りっぱなしや立ちっぱなしを避ける、身体を冷やさないなどが重要です。食事療法は、食物繊維を多く含む食品や水分を積極的に摂り、便を柔らかくして排便をスムーズにします。
薬物療法では、軟膏・坐薬で炎症を抑えたり、痛みや出血を和らげたりします。内服薬として、便を柔らかくする下剤、炎症を抑える薬、血管を強くする薬などを処方することがあります。
手術治療
保存的治療で効果が見られない場合や、症状が進行している場合は手術が検討されます。手術方法は、疾患の種類や肛門の状態などによって異なります。
それぞれの治療法について十分な説明を受け、メリット・デメリットも踏まえたうえで選択することが大切です。
新潟で肛門外科を受診するなら松波クリニックへ
新潟で肛門外科をお探しの際は、松波クリニックまでご相談ください。患者様の負担を最小限にするため、通院治療を主体に、親切丁寧な診療を心がけております。手術が必要な場合も、入院ではなく日帰り手術を行います。火曜日の19:00~21:00は夜間診療、土曜日は午前診療に対応しております。初診の方は、午前8:30~12:00/午後15:30~18:00までにご来院ください。
【新潟】肛門外科・内科治療、いぼ痔や切れ痔に役立つコラム
- 【新潟】肛門が痒い原因とは?市販薬使用時の注意点や肛門外科受診の重要性
- 【新潟】肛門の痛みの原因・放置するリスク・肛門外科の診察内容
- 【新潟】肛門から出血を引き起こす疾患や肛門外科受診の目安について
- 【新潟】肛門内科の受診は恥ずかしい?配慮のポイントと早期受診のメリット
- 【新潟】肛門内科で対応する症状や診察の流れ・検査内容とは?
- 【新潟 肛門内科】便秘の特徴・生活習慣の見直しポイント・排便習慣の作り方
- 【新潟】いぼ痔の悪化を防ぐ!座り方と日常生活でできる予防法
- 【新潟】いぼ痔の進行段階や症状を悪化させるNG習慣とは?
- 【新潟】切れ痔の放置は危険信号!悪化・再発を防ぐための対処法
- 【新潟】切れ痔の悪化を防ぐには?排便習慣とトイレのコツ