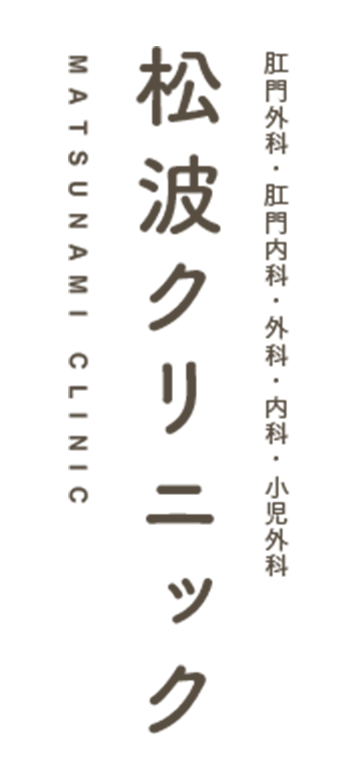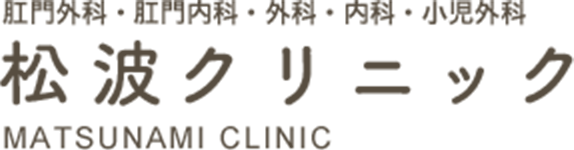【新潟】肛門の痛みの原因・放置するリスク・肛門外科の診察内容
【新潟】肛門の痛み…考えられる原因とは?放置するリスクや肛門外科の診察内容も解説
肛門の痛みは周囲に話しにくいデリケートな症状で、誰にも相談できず、一人で悩みを抱えている方もいます。その痛みの背景にはさまざまな原因が隠れており、場合によっては早期の治療が必要なケースもあります。こちらでは、肛門の痛みの種類や原因、放置によるリスク、肛門外科での診察内容について解説します。新潟周辺で肛門の痛みにお悩みの方は、ぜひご一読いただければと思います。
肛門が痛いのはなぜ?痛みの種類と原因

肛門の痛みと言っても、その感じ方や症状は人それぞれです。ズキズキと脈打つような痛み、排便時にのみ発生する痛み、座っているときに感じる痛みなど、各症状に応じて示唆される疾患は異なります。
いぼ痔(痔核)による痛み
いぼ痔(痔核)は、肛門の痛みの中でも特に多い原因の一つです。肛門の内側にできる内痔核と、外側にできる外痔核に分類されます。
内痔核の痛み
内痔核は、通常は痛みを伴いません。排便時に出血したり、いきみでいぼが肛門の外に脱出(脱肛)した際に、初めて痔に気づくケースが多いです。症状が進行すると、炎症による痛みが生じます。また、脱肛したままの内痔核が肛門括約筋に締め付けられる「嵌頓痔核(かんとんじかく)」の状態になると、患部が大きく腫れ、激しい痛みを伴います。緊急性の高い状態であり、すぐに医療機関を受診する必要があります。
外痔核の痛み
外痔核は、肛門の皮膚に近い部分にできるため、内痔核に比べて痛みを強く感じる傾向があります。特に、血栓が形成されて急激に腫れ上がる「血栓性外痔核」は、突然の激しい痛みを引き起こします。触れると硬いしこりのようなものが確認され、座るのもつらいほどの痛みを伴う場合もあります。
切れ痔(裂肛)による痛み
切れ痔(裂肛)も原因の一つです。主に硬い便の排出時や、勢いよく便が出た際に、肛門の皮膚が切れることで起こります。
切れ痔の痛みは、排便時に肛門が裂けるような鋭い痛みが特徴です。排便後もしばらく痛みが続いたり、灼熱感を感じたりすることもあります。出血を伴うことも多く、トイレットペーパーに鮮血が付着する、便器の水が赤くなるなどの症状が見られます。何度も繰り返すと、慢性化して潰瘍になったり、肛門が狭くなったりすることもあります。
痔瘻(あな痔)による痛み
痔瘻(あな痔)は、直腸と肛門周囲の皮膚がトンネル状につながり、そこから膿が排出される病態を指します。
痔瘻は、はじめに肛門周囲に膿がたまる「肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)」という状態から始まります。この時期は、発熱を伴う激しい痛みや腫れ、熱感が生じます。膿瘍が破れて膿が出ると一時的に痛みは和らぎますが、根本的な治療をしない限り、膿のたまりと排出を繰り返し、症状が進行します。痔瘻が形成されると、慢性的な痛みや違和感、下着の汚染などが続くようになります。自然治癒はほとんど期待できず、手術が必要になることが多いです。
その他の原因
上記以外にも、肛門の痛みを引き起こす疾患が存在します。
肛門挙筋症候群
肛門周囲の筋肉が痙攣することで起こる痛みです。周期的に激しい痛みが起こり、多くの場合、夜間や明け方に痛みを感じやすいです。原因は不明な点が多く、ストレスや疲労が関与している可能性が指摘されます。
直腸肛門痛
特定の原因が見つからないにもかかわらず、肛門や直腸に慢性的な痛みを感じる状態です。過敏性腸症候群(IBS)や精神的なストレスとの関連も指摘されています。
炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎など)
大腸や小腸に炎症が起こる病気で、肛門周囲に症状が現れることがあります。痔瘻のような症状や、慢性の下痢、腹痛などを伴います。
ヘルペスや淋病といった性感染症、肛門周囲皮膚炎、坐骨神経痛、大腸がん、肛門がんなどが原因のこともあります。自己判断せずに、まずは医師に相談することが大切です。
我慢するとどうなる?痛みを放置するリスク

「多少の痛みなら大丈夫」「肛門外科に行くのは恥ずかしい」と、肛門の痛みを我慢していませんか。しかし、肛門の痛みを放置することは、症状の悪化や他疾患の見逃しのリスクが伴います。
症状の悪化と慢性化
肛門の痛みを引き起こす疾患の多くは、放置することで症状が悪化および慢性化する傾向があります。例えば、初期の内痔核は、生活習慣の改善によって症状が落ち着くことがある一方、放置すると徐々に悪化し、排便時以外にも脱肛するなど、日常生活に支障をきたす可能性があります。
また、切れ痔は一度で治癒する場合もありますが、硬い便の排出を繰り返すことで傷が深くなり、治癒が困難になります。慢性化すると、肛門の皮膚が硬く厚くなったり、ポリープができたり、さらには肛門が狭くなる「肛門狭窄」を引き起こし、排便が困難になる場合もあります。この段階に至ると、手術が必要になる場合が多いです。
日常生活への影響
肛門の痛みが続くと、日常生活にも大きな影響を及ぼします。
排便時の苦痛と排便習慣の変化
排便時の痛みや出血が怖くなり、排便を我慢することがあります。これは便秘を引き起こし、さらに排便時の痛みを増強させる悪循環に陥ります。また、便秘薬に頼りすぎたり、排便に過度な時間をかけたりするなど、不健康な排便習慣が定着してしまうこともあります。
精神的な負担とストレス
長引く痛みは精神的なストレスにもつながります。外出や旅行をためらったり、仕事に集中できなかったりするなど、生活の質が著しく低下する可能性もあります。
見過ごされる重篤な病気のリスク
肛門の痛みは痔に限らず、炎症性腸疾患、大腸がん、肛門がんといった重篤な病気の初期兆候の可能性もあります。痛みを「ただの痔だろう」と自己判断して放置することで病気の発見が遅れ、手遅れになってしまうことも否定できません。出血や体重減少、発熱などの症状を伴う場合は、早急に医療機関の受診が必要です。
痛みを我慢することは、百害あって一利なしです。早期に医療機関を受診し、適切な診断と治療を行うことで、症状の悪化を防ぎ、より早く快適な日常生活を取り戻すことができます。
肛門外科での診察・検査内容
一般的な肛門外科での診察・検査の内容についてご紹介します。
問診
まず、医師による問診が行われます。症状を正確に把握し、適切な診断につなげるために重要なプロセスです。恥ずかしがらずに、気になる症状を正直に伝えましょう。
視診・触診
問診後、実際に肛門の状態を診察します。医師の目で、痔核の有無、腫れ、ただれ、切れ痔の傷、皮膚の状態などを観察します。視診だけでも、ある程度の病状を把握することができます。次に、肛門にゆっくりと指を挿入し、筋肉の締まり具合、直腸の粘膜の状態、内痔核の有無や大きさ、腫瘍の有無などを調べます。痔核の脱出度合いや、痔瘻のトンネルの方向などを確認することもできます。
肛門鏡検査
肛門鏡検査は、肛門鏡を使って肛門内部を直接観察するための検査です。指診と同じような体勢をとり、医師が肛門鏡をゆっくりと挿入し、内痔核の状態、直腸の粘膜の炎症、ポリープの有無などを詳細に観察します。痛みはほとんどありませんが、肛門鏡を挿入する際に圧迫感を覚えることがあります。
医師は患者様のプライバシーに配慮し、できる限り苦痛の少ない方法で検査を進めます。肛門の痛みでお悩みの際は、まずは肛門外科の受診をご検討ください。
おしりのトラブルを解決するなら新潟の松波クリニックへ
肛門の痛みでお困りの際は、新潟の松波クリニックまでご相談ください。おしりの「悩み」や「心配事」を解決し、患者様に快適な環境をご提供いたします。日常生活や排便習慣の改善に関するサポートもお任せください。
【新潟】肛門外科・内科治療、いぼ痔や切れ痔に役立つコラム
- 【新潟】肛門が痒い原因とは?市販薬使用時の注意点や肛門外科受診の重要性
- 【新潟】肛門の痛みの原因・放置するリスク・肛門外科の診察内容
- 【新潟】肛門から出血を引き起こす疾患や肛門外科受診の目安について
- 【新潟】肛門内科の受診は恥ずかしい?配慮のポイントと早期受診のメリット
- 【新潟】肛門内科で対応する症状や診察の流れ・検査内容とは?
- 【新潟 肛門内科】便秘の特徴・生活習慣の見直しポイント・排便習慣の作り方
- 【新潟】いぼ痔の悪化を防ぐ!座り方と日常生活でできる予防法
- 【新潟】いぼ痔の進行段階や症状を悪化させるNG習慣とは?
- 【新潟】切れ痔の放置は危険信号!悪化・再発を防ぐための対処法
- 【新潟】切れ痔の悪化を防ぐには?排便習慣とトイレのコツ