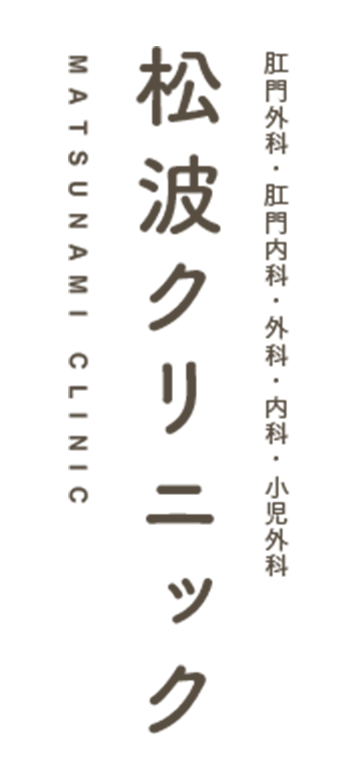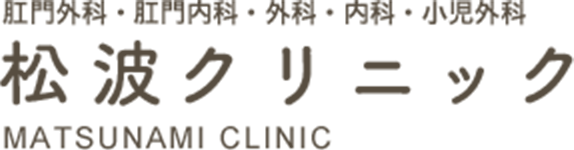【新潟】切れ痔の放置は危険信号!悪化・再発を防ぐための対処法
【新潟】切れ痔を放置するリスクとは?再発予防のコツなども解説
排便時に強い痛みや出血を伴う切れ痔(裂肛)ですが、「そのうち治るだろう」と放置されることも少なくありません。しかし、適切な対処を行わずにいると、慢性化や潰瘍化につながるおそれがあります。こちらでは、切れ痔を放置した場合のリスク、自然治癒の限界、再発予防のコツを解説いたします。新潟周辺で切れ痔の治療を希望している方も参考にしていただければと思います。
切れ痔を放置するとどうなる?初期症状から慢性化・潰瘍のリスクまで

切れ痔(裂肛)は、排便時に肛門の皮膚が切れてしまう状態です。いぼ痔(痔核)は男女ともに見られますが、切れ痔は比較的女性に多い傾向があります。
切れ痔の初期症状
切れ痔の主な初期症状は、痛みと出血です。排便時に肛門にピリッとした痛みを感じたり、トイレットペーパーに少量の血液が付着したりします。痛みはしばらくすると治まり、また、大量に出血することはまれです。初期であれば、生活習慣の見直しや市販薬によって症状が落ち着くこともあります。
放置による慢性化・潰瘍化のリスク
切れ痔を放置すると、症状は徐々に悪化の一途をたどることになります。初期の切れ痔は、排便時の痛みで済むことが多いですが、炎症が繰り返されることで傷口が治らず、常に肛門に痛みや不快感を抱えるようになります。また、慢性的な切れ痔は、肛門の皮膚が硬く盛り上がって見張りイボや、肛門ポリープができることがあります。
また、排便時の激しい痛みから無意識のうちに便意を我慢し、便秘を悪化させるなど、負のループに陥ることも少なくありません。
肛門括約筋まで傷が及ぶと、肛門自体が狭くなります(肛門狭窄)。ますます便が出にくい状態であり、通過するときに肛門が切れやすく、炎症が続くことで、症状が悪化してしまいます。
自然治癒できる?市販薬や自己処置に頼りすぎるリスク

軽度の切れ痔であれば、生活習慣の改善によって回復することもあります。ただし、自己判断で対処し続けることには注意が必要です。処置の方法を誤ると、かえって症状が悪化するかもしれません。
軽度の切れ痔と自然治癒の可能性
軽度の切れ痔は、排便習慣の見直し、便秘の改善、肛門を清潔に保つなど、適切なケアを心がけることで、自然に回復へ向かうケースもあります。市販の塗り薬などを使用して痛みや炎症を和らげながら、生活習慣を整えていくのが基本的な対処法です。
自己処置の限界と注意点
ただし、市販薬や自己処置に頼り続けることには限界があります。例えば、肛門を清潔に保つつもりでゴシゴシと洗ったり、刺激の強い石けんを使ったりすると、かえって皮膚を傷つけてしまう可能性があります。また、市販薬は症状を一時的に抑えるためのものであり、状態によっては根本的な改善につながらないこともあります。使用方法を誤ると副作用が出たり、症状が悪化したりすることもあります。
こうした処置で症状が長引いたり、再発を繰り返したりする場合は、医療機関で診断を受けることが重要です。気になる症状があるときは、早めに医師に相談することをおすすめします。
切れ痔が治らないときは?肛門外科での治療と再発予防のコツ
切れ痔はデリケートな悩みだからこそ、肛門外科での適切な診断と治療が必要です。加えて、治療後も再発を防ぐための生活習慣の改善が重要となります。
肛門外科での診断と治療
肛門外科では、症状や体調などを総合的に判断し、一人ひとりに合った治療法が選ばれます。
診察
まず、医師が症状や生活習慣について詳しく問診します。その後、視診・触診、肛門鏡を使った検査が行われます。肛門鏡を使うことで、痔の有無や種類、状態を直接確認することができ、診断に役立ちます。検査は短時間で終わり、身体への負担も大きくありません。
治療法
切れ痔の治療は、症状の程度や原因に応じて段階的に進められます。軽度から中程度の場合、まずは薬や生活習慣の見直しといった保存的治療が選択されます。治療薬には、炎症を抑える軟膏や坐薬、便をやわらかくする内服薬などが使われることが多く、排便時の負担を減らすことが目的です。加えて、便秘の改善や肛門周囲の清潔保持、排便習慣の工夫について、医師から具体的なアドバイスが行われます。
こうした方法で十分な改善が見込めない場合や、潰瘍が深くなっていたり、見張りイボ・肛門狭窄などがあるときには、手術が検討されます。手術と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、日帰りで受けられるケースもあり、身体への負担が少ない方法も増えています。代表的な手術には、肛門の筋肉の緊張をゆるめる「内括約筋側方皮下切開術」や、肛門狭窄を広げるための処置などがあります。いずれも痛みを和らげ、排便しやすい状態に整えることを目的としています。
切れ痔の再発を防ぐためのアドバイス
切れ痔は、一度よくなっても生活習慣によって再発することがあります。治療後も快適に過ごすためには、日々のちょっとした工夫がポイントになります。
便秘の予防を意識する
便秘は切れ痔の大きな原因の一つです。排便をスムーズにするために、次のような習慣を心がけてみてください。
- 食物繊維をとる:野菜、果物、きのこ、海藻などに多く含まれます。水溶性食物繊維は便をやわらかく保つのに役立ちます。
- 水分をしっかりとる:1日1.5~2リットルが目安。朝起きたときの1杯の水は、腸を動かすきっかけになります。
- 軽く身体を動かす:ウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で身体を動かすことも大切です。
正しい排便習慣を身につける
- 毎日同じ時間にトイレへ:決まったタイミングでトイレに行くと、自然に排便しやすくなります。
- いきまずにリラックスする:強くいきむと肛門に負担がかかります。自然な排便を心がけましょう。
- トイレは短時間で:スマホや読書は控え、3~5分程度で済ませるようにすると血流の悪化を防げます。
肛門周りを清潔に保つ
排便後は温水洗浄便座やシャワーで優しく洗い、清潔に保ちます。ただし、洗いすぎは禁物です。皮膚のバリアが弱くなることがあるため、石けんの使用は控えめにしましょう。
身体を冷やさないようにする
特に下半身の冷えには注意が必要です。冷えによって血行が悪くなると、肛門周囲のうっ血を招きやすくなります。湯船に浸かる、腹巻きを使うなど、身体を温める工夫が効果的です。
ストレスを溜め込まない
ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、便秘や下痢の原因になります。趣味や休息を取り入れて、気分転換の時間を作るようにしましょう。
同じ姿勢を長時間続けない
長時間の座りっぱなしや立ちっぱなしは、肛門まわりの血行を悪くします。仕事中でもこまめに立ち上がったり、軽く身体を動かしたりすることが、切れ痔の予防につながります。
切れ痔は、早めに対処することで日常生活への影響を軽減できます。症状が落ち着いた後もこうした習慣を意識し、再発しにくい状態を保ちましょう。
切れ痔の治療をご希望なら新潟の松波クリニックへ
新潟の松波クリニックでは、切れ痔をはじめ、肛門の不調に幅広く対応しております。プライバシーに配慮した環境で、患者様一人ひとりに寄り添った検査や治療を行います。日常生活や排便習慣の改善もサポートいたします。おしりに関する悩み・心配事がありましたら、松波クリニックまでご相談ください。
【新潟】肛門外科・内科治療、いぼ痔や切れ痔に役立つコラム
- 【新潟】肛門が痒い原因とは?市販薬使用時の注意点や肛門外科受診の重要性
- 【新潟】肛門の痛みの原因・放置するリスク・肛門外科の診察内容
- 【新潟】肛門から出血を引き起こす疾患や肛門外科受診の目安について
- 【新潟】肛門内科の受診は恥ずかしい?配慮のポイントと早期受診のメリット
- 【新潟】肛門内科で対応する症状や診察の流れ・検査内容とは?
- 【新潟 肛門内科】便秘の特徴・生活習慣の見直しポイント・排便習慣の作り方
- 【新潟】いぼ痔の悪化を防ぐ!座り方と日常生活でできる予防法
- 【新潟】いぼ痔の進行段階や症状を悪化させるNG習慣とは?
- 【新潟】切れ痔の放置は危険信号!悪化・再発を防ぐための対処法
- 【新潟】切れ痔の悪化を防ぐには?排便習慣とトイレのコツ