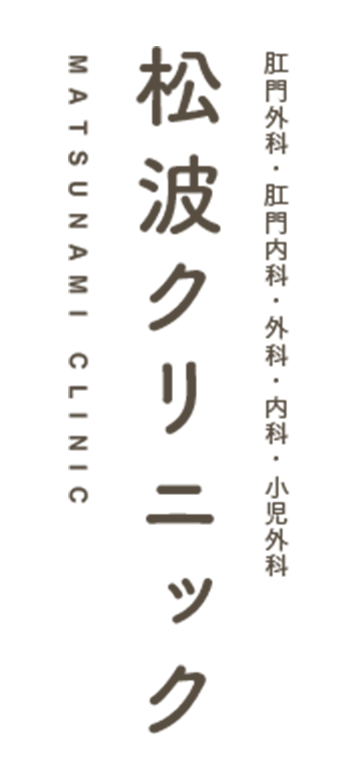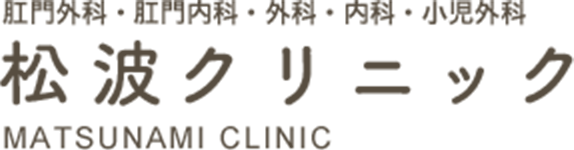【新潟】いぼ痔の進行度や症状を悪化させるNG習慣とは?
【新潟】いぼ痔の進行度や悪化のサインとは?日常生活で気をつけたいNG習慣なども解説
いぼ痔は誰にでも起こり得る身近な症状です。新潟周辺でも、いぼ痔に悩む方は男女問わずいます。こちらでは、いぼ痔の進行度、悪化のサイン、日常生活で気をつけたい習慣、肛門外科で行う治療について解説いたします。
いぼ痔はどこまで進行すると危険?悪化する前に知っておきたい症状の変化

いぼ痔には、内痔核と外痔核の2種類があります。一般的に、いぼ痔といえば内痔核を指すことが多いです。内痔核はほとんど痛みを感じないものの、進行するにつれていぼが大きくなり、肛門から飛び出します。この「脱出」の程度によって、4段階に分類されます(Goligher分類)。
I度:肛門から脱出しない
I度は、いぼ痔の初期段階です。この段階では、まだ肛門の内側にとどまっており、排便時に外へ飛び出すことはありません。主な症状としては、排便時の出血が挙げられます。トイレットペーパーに血液が付着したり、便器の水が赤く染まったりすることで気づくケースが多いです。痛みはほとんど感じられず、保存的治療や市販薬によるセルフケアで対処できます。
II度:肛門から脱出するが、自然に戻る
排便時に脱出するものの、排便後、自然に肛門内に戻るのが特徴です。出血に加え、脱出することで肛門周囲に不快感、かゆみ、痛みを感じることがあります。脱出した際に衣類との摩擦や、座ったときの圧迫により、不快感が増すことがあります。また、戻る際に軽度の痛みや違和感が生じるケースもあります。
III度:指で押し込まないと戻らない
排便後、指で押し込まないと元に戻らない状態です。この段階になると、日常生活において著しい不快感や痛みが現れます。また、脱出した時間が長くなると炎症が生じやすく、激しい痛みや腫れを伴うこともあります。また、いぼ痔を押し戻す手間から精神的な負担が増大し、生活の質に深刻な影響を与える可能性があります。なお、単なる生活習慣の改善や市販薬による対処だけでは、症状の根本的な改善は期待しにくい状況です。
IV度:常に肛門から脱出した状態
いぼ痔が常に肛門の外に脱出した状態です。指で押し込んでも戻らない、すぐにまた飛び出してしまいます。この段階になると、激しい痛み、出血、炎症、さらには感染のリスクが非常に高くなり、日常生活に甚大な影響を及ぼします。常に外部に露出しているため、下着が汚れたり、座る動作や歩行が困難になることもあります。III度と同じく、根本的な改善には手術が必要となります。
外痔核の悪化のサイン
外痔核は、肛門の外側にできるいぼ痔です。内痔核と異なり皮膚上に生じるため、痛みを伴います。さらに、肛門周囲に血栓(血液の塊)が形成される血栓性外痔核の場合は、より激しい痛みが特徴です。急に肛門周辺に硬いしこりができ、強い痛みが現れた場合は、血栓性外痔核の可能性が疑われます。
進行度が上がるほど治療に要する期間が延びるため、早期の対処が重要です。
知らずにやっている?いぼ痔を悪化させるNG習慣

いぼ痔の症状を悪化させる原因は多岐にわたりますが、日々のちょっとした習慣が進行を早めたり、不快な症状を引き起こしたりする可能性があります。
便秘・下痢
便秘と下痢は、肛門に強い刺激や圧力を与え、痔の悪化を招きやすく、症状を繰り返す要因にもなります。
便秘の場合、硬い便を排出しようといきむことで、肛門の血管に強い圧がかかり、うっ血が進み、いぼ痔が腫れたり、脱出します。さらに、硬い便による摩擦で傷付き、出血や痛みを引き起こすこともあります。加えて、腸内に便が長くとどまると悪玉菌が増殖しやすく、腸内環境の悪化によって腹部の張りや不快感が生じることもあります。
一方、下痢も油断できません。水分の多い便が勢いよく排出されることで、肛門の粘膜や血管が刺激を受け、炎症や痛みの原因になります。頻繁な排便により肛門周囲がただれ、未消化の刺激物がかゆみを引き起することもあります。
長時間同じ体勢
長時間、同じ姿勢を続けることは、いぼ痔の悪化を招く要因です。座りっぱなしだと、お尻全体に体重がかかるため、肛門の血管が圧迫されます。血流が悪くなることでうっ血し、腫れたり、症状が重くなったりします。柔らかいソファやクッションに深く腰掛けた状態も、お尻が沈み込んで圧力が集中するため、負担が大きくなります。
また、立ち続けていると、重力の影響で血液が下半身に滞留し、肛門周囲の血管に負担がかかります。これにより、腫れや痛みが生じる可能性があります。
食生活の乱れ
日々の食生活は、いぼ痔の症状に大きく影響します。食物繊維は便のかさを増やし、適度な水分を含ませることで、スムーズな排便を促します。不足すると便が硬くなり、便秘につながります。
香辛料やアルコールもいぼ痔を刺激する要因です。唐辛子などは、消化されずに腸を通過し、便とともに肛門に到達します。この刺激が、いぼ痔にダメージを与え、痛みや出血を悪化させることがあります。また、アルコールには血管を拡張させる作用があり、いぼ痔のうっ血を促進するおそれもあります。
無理なダイエットと冷え
極端な食事制限を伴うダイエットでは、食物繊維や水分の摂取量が減り、便秘を引き起こします。さらに、食事量が少ないことで腸の働きが低下し、排便のリズムも乱れがちです。また、下腹部や腰まわりが冷えると肛門周辺の血流が滞り、いぼ痔のうっ血や腫れを招きます。冬場はもちろん、夏場の冷房による冷えにも注意が必要です。
いぼ痔の治療法!肛門外科で行われる処置とは
いぼ痔の治療は、症状の進行度合いによって大きく異なります。症状が進行している場合は、肛門外科での専門的な治療が必要です。
保存的治療
保存的治療は、主にいぼ痔の初期段階や、症状が比較的軽い場合に選択される治療法です。手術をせずに、薬や生活習慣の改善によって症状の緩和を目指します。
薬による治療
いぼ痔の薬には、主に内服薬と外用薬があります。内服薬は、炎症や出血を抑える作用、便を柔らかくする作用などを持つ薬が処方されます。これらの薬は、症状に合わせて組み合わせることもあります。外用薬には、ステロイド配合の軟膏や坐剤、非ステロイド性の抗炎症剤などがあります。
生活習慣の改善指導
薬による治療と並行して、生活習慣の改善に取り組みます。まず、便通を整える食生活では、バランスの取れた食事が重要です。栄養バランスの取れた食事を心がけ、さらに野菜・果物・きのこ類・海藻類・豆類など、食物繊維を豊富に含む食品を積極的に摂りましょう。また、十分な水分補給も欠かせません。1日あたり1.5~2リットルを目安に、こまめに水分を摂取しましょう。
排便習慣の見直しも行います。毎朝決まった時間にトイレに行く習慣をつけ、便意を感じたら我慢せずすぐにトイレに行きましょう。無理ないきみを避けるため、1回の排便時間は3~5分程度を目安にします。
また、湯船に浸かることで、肛門周囲の血行が促進されます。シャワーだけでなく、毎日ゆっくり湯船に浸かる習慣をつけましょう。
非手術的治療
保存的治療で改善が見られない場合や、症状が進行している場合に選択されるのが非手術的治療です。手術を伴わないため、身体への負担が少ないのが特徴です。
ALTA療法(痔核硬化療法)
ALTA療法は、内痔核に薬液を注入して固める治療法です。切らずに治療できるため、負担が少なく、日帰りでの治療も可能です。通常、10分程度で終了します。治療の効果は数週間から数ヶ月かけて現れます。また、痔核の大きさや状態によっては、複数回の治療が必要です。
輪ゴム結紮療法
輪ゴム結紮療法は、特殊な器具を用いて痔核の根元をゴムで縛り、血流を遮断することで痔核を壊死させる治療法です。ALTA療法と同じく、切らずに治療できるため、身体への負担が少ないのが特徴です。痔核が脱落する際に、少量の出血や便に混じった血栓が見られます。
手術療法
いぼ痔が重度に進行している場合(III度~IV度)や、保存的治療や非手術的治療で効果が見られない場合に選択されます。根本的な解決を目指すため、再発のリスクを低減できるメリットがあります。
痔核切除術(結紮切除術)
いぼ痔そのものを切除し、根元を縫い合わせて止血します。内痔核と外痔核の両方に有効です。手術時間は、痔核の数や大きさによって異なり、通常は30分~1時間程度です。入院が必要な場合もありますが、日帰り手術に対応している医療機関もあります。
新潟でいぼ痔の治療を希望するなら松波クリニックへ
いぼ痔の症状は、進行度合いによって適切な治療法が異なります。早めに肛門外科・肛門内科を受診し、症状の改善を目指しましょう。新潟の松波クリニックでは、患者様一人ひとりに合わせて親切丁寧な診療を心がけております。おしりの悩み・心配事がありましたら、お気軽にご相談ください。
【新潟】肛門外科・内科治療、いぼ痔や切れ痔に役立つコラム
- 【新潟】肛門が痒い原因とは?市販薬使用時の注意点や肛門外科受診の重要性
- 【新潟】肛門の痛みの原因・放置するリスク・肛門外科の診察内容
- 【新潟】肛門から出血を引き起こす疾患や肛門外科受診の目安について
- 【新潟】肛門内科の受診は恥ずかしい?配慮のポイントと早期受診のメリット
- 【新潟】肛門内科で対応する症状や診察の流れ・検査内容とは?
- 【新潟 肛門内科】便秘の特徴・生活習慣の見直しポイント・排便習慣の作り方
- 【新潟】いぼ痔の悪化を防ぐ!座り方と日常生活でできる予防法
- 【新潟】いぼ痔の進行段階や症状を悪化させるNG習慣とは?
- 【新潟】切れ痔の放置は危険信号!悪化・再発を防ぐための対処法
- 【新潟】切れ痔の悪化を防ぐには?排便習慣とトイレのコツ