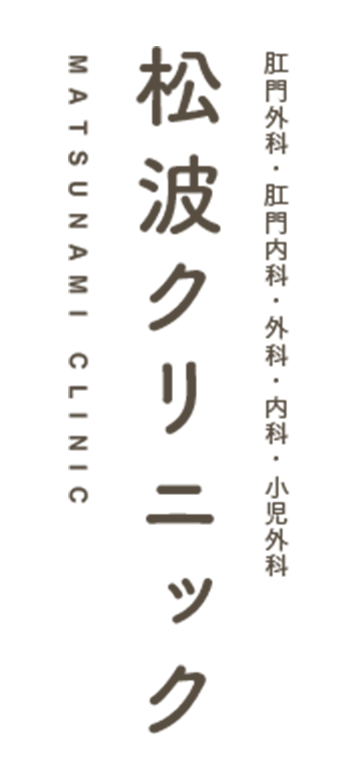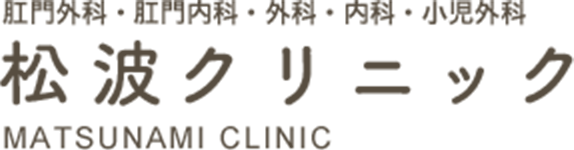【新潟 肛門内科】便秘の特徴・生活習慣の見直しポイント・排便習慣の作り方
【新潟】肛門内科に相談を!便秘の特徴・生活習慣の見直しポイント・排便習慣の作り方などを解説
便秘が続くと不快感だけでなく、痔などの肛門トラブルにつながることもあります。「新潟の肛門内科で診てもらえるのか」「何科を受診すればいいのか」と迷う方も多いかもしれません。こちらでは、肛門内科で診察を受ける便秘の特徴、生活習慣の見直しポイント、排便習慣の作り方などについて解説いたします。
肛門内科が対応する便秘とは?痔や直腸との関係にも注目

便秘の定義と種類
一般的に便秘とは、
- 排便が週に3回未満
- 排便時に強い力みが必要
- 硬い便
- 残便感がある
などの状態が慢性的に続くことを指します。単に排便回数が少ないだけでなく、排便に苦痛を伴ったり、生活の質が低下したりする場合も便秘とみなされます。
便秘はメカニズムによって、機能性便秘と器質性便秘に分けられます。
機能性便秘
生活習慣やストレスなどの影響を受け、大腸の運動や働きが低下することで起こる便秘です。機能性便秘は3種類に分類され、一般的に便秘と呼ばれるものは、いずれかに該当します。
- 弛緩性便秘:大腸の運動が低下し、便を送り出す力が弱まることで起こります。女性や高齢者に多く見られます。
- 痙攣性便秘:ストレスなどの影響で大腸が過度に収縮し、便の通過が阻害されることで起こります。コロコロとした兎糞状の便が特徴です。
- 直腸性便秘:便が直腸に到達しても便意を催さず、直腸内に停滞することで起こります。便意を我慢してしまう方に多く見られます。
機能性便秘は、生活習慣の見直しによって症状の改善が期待されます。
器質性便秘
器質性便秘は、腫瘍、炎症、癒着、潰瘍などにより、物理的に便通が妨げられることで起こる便秘です。大腸がんや大腸ポリープ、炎症性腸疾患などが主な原因として考えられます。便秘の症状だけでなく、血便や腹痛、体重減少などの症状を伴うことがあります。器質性便秘の場合、まずは原因となる疾患の治療が優先されます。重篤な疾患を見落とさないためにも、自己判断せず、早めに医療機関で検査を受けることが重要です。
便秘・痔・直腸の密接な関係
便秘、痔、直腸は互いに密接な関係にあります。例えば、便が硬くなると排便時に過度な力みが生じ、この力みが肛門周辺の血管に負担をかけ、痔を悪化させたり、新たな痔の原因となったりします。また、硬い便が肛門を通過する際、肛門の皮膚や粘膜を傷つけ、切れ痔を引き起こすこともあります。慢性的な便秘は肛門に持続的な負担をかけ、痔の症状が改善しにくい状態を招きます。
また、直腸は便を一時的に貯留し、排便時に便を肛門へ送り出す重要な役割を担っています。しかし、直腸の機能が低下すると、便秘を引き起こす要因となります。
肛門内科では便秘に加え、痔や直腸の問題も総合的に診断し、適切な治療を実施することが可能です。
肛門内科で行う便秘治療!生活習慣の見直しと診断のポイント
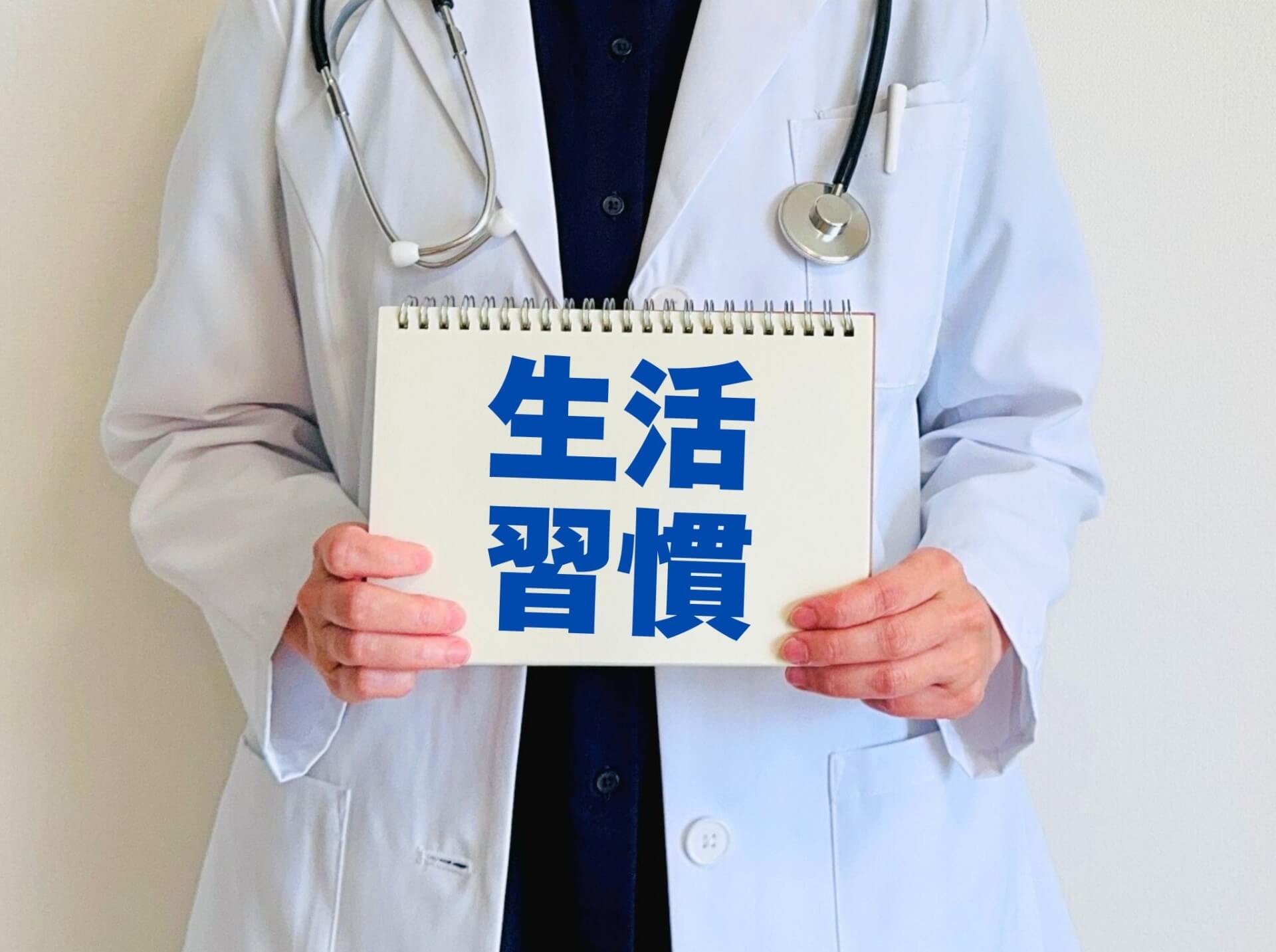
便秘の治療は、単に下剤を処方するだけではありません。便秘の原因は多岐にわたるため、一人ひとりの状況に合わせた総合的なアプローチで、便秘の改善を目指します。
便秘治療の基本となる生活習慣の改善
便秘の改善には、日々の生活習慣を見直すことが重要です。特に機能性便秘の場合、生活習慣の見直しが症状の軽減に直結することが多くあります。
バランスの取れた食事と水分摂取
便秘の予防や改善には、食物繊維や水分を意識的に摂ることが大切です。食物繊維には便のカサを増やし、排便を促す働きがあります。特に、水溶性食物繊維(わかめ、こんぶ、果物など)は便を柔らかくし、不溶性食物繊維(野菜、きのこなど)は便の量を増やします。野菜、果物、きのこ類、海藻類、豆類、全粒穀物などをバランス良く組み合わせることで、腸内環境の改善にもつながります。
また、水分補給も欠かせません。水分量が不足すると便が硬くなり、排出しにくくなるため、1日あたり1.5~2リットルを目安に、こまめに水を飲む習慣をつけましょう。朝起きてすぐにコップ1杯の水を飲むと、腸の動きを刺激する効果が期待できます。
さらに、ヨーグルトや納豆、味噌などの発酵食品には、腸内の善玉菌を増やす働きがあり、腸内環境を整えるうえで役立ちます。日々の食事に取り入れて、腸の調子をサポートしましょう。
適度な運動習慣
運動不足は、腹筋の衰えや腸の動きの低下につながり、便秘を引き起こしやすくなります。ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなど、自分のペースで身体を動かす習慣をつけましょう。中でも、腹筋を意識した運動は、排便時に必要な腹圧を高めるうえで効果が期待できます。
ストレスの管理
ストレスは自律神経のバランスを乱し、腸の働きにも影響を及ぼすことがあります。趣味の時間を持つ、十分な睡眠をとるなど、ストレスを上手に和らげることが、腸の調子を整える助けになります。
便秘治療における薬物療法の選択肢
生活習慣の改善だけでは症状が十分に改善しない場合や、迅速な症状の緩和が求められる場合には、薬物療法が検討されます。例えば、酸化マグネシウムなどの浸透圧性下剤は、腸内に水分を引き寄せることで便を柔らかくし、排便を促します。刺激性下剤は大腸を刺激し、蠕動運動を促すことで排便させます。また、漢方薬の処方、坐薬や浣腸が用いられることもあります。
肛門内科では、便秘のタイプや症状の程度などに応じて、適切な薬剤を処方します。
便秘を放置すると痔が悪化する?快適な排便習慣の作り方
慢性的な便秘は痔の発生や悪化に深く関わっており、放置することで症状が重くなり、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
便秘を放置するリスク
便秘が続くと、排便時に過度な力みが生じ、肛門に大きな負担がかかります。その結果、痔の悪化や新たな痔の発生につながることがあります。
便が硬くなると、いぼ痔(痔核)が形成されやすくなり、進行すると肛門から突出する「脱肛」や、強い痛みを伴う「嵌頓(かんとん)」が生じることもあります。また、切れ痔(裂肛)は再発を繰り返すことで慢性化し、肛門が狭く硬直する「狭窄」を引き起こす場合があります。このような状態が続くと、排便がますます困難になり、悪循環に陥ってしまいます。
さらに、便秘は痔だけでなく、次のような体の不調を招くこともあります。
- 腹部の張りや腹痛
- 肌荒れやニキビ
- 肩こりや頭痛
- イライラや気分の落ち込み
こうした不調は、便秘を放置することにより悪化し、生活の質を低下させる原因となります。
快適な排便習慣を作るには
快適な排便習慣を保つためには、薬や治療だけでなく、毎日の積み重ねが重要です。以下のような工夫や心がけを続けることで、排便トラブルの予防や改善につながります。
生活習慣の見直し
食事・運動・睡眠といった基本的な生活習慣は、排便リズムに大きく影響します。食物繊維や水分をしっかり摂り、適度に身体を動かし、ストレスを溜めすぎないように心がけましょう。こうした積み重ねが、自然な排便をサポートします。
排便時の工夫と姿勢
排便時に不必要な力みを避けることも大切です。
- 正しい排便姿勢:便座に深く座り、少し前傾姿勢になることで、直腸と肛門の角度がまっすぐになり、排便がスムーズになります。踏み台を使って足元を高くするのも効果的です。
- いきみすぎない:呼吸を意識し、ゆっくりと息を吐きながら、自然な力みで排便しましょう。強くいきむと肛門に負担がかかり、痔の悪化につながります。
- 冷やさない:肛門周囲を冷やすと血行が悪くなり、痔の症状が悪化することがあります。温かいお湯でシャワーを浴びたり、温水便座を使用したりして、肛門を冷やさないように心がけましょう。
日々の変化に注意する
症状に変化があれば、我慢せず医師に相談しましょう。排便の状態や痛み、出血などの変化は、治療の見直しが必要なサインかもしれません。
快適な排便習慣を作るには、治療と並行して生活習慣の見直しや排便時の工夫を積み重ねることが大切です。日々のちょっとした心がけが、症状の改善や再発予防につながります。
便秘の悩みを相談するなら新潟の松波クリニックへ
便秘や下痢、痔などのお悩みを解決するなら、新潟の松波クリニックまでご相談ください。火曜日は19:00~21:00までの夜間診療、土曜日は午前8:30~12:30まで開院しております。初診の方は、午前8:30~12:00/午後15:30~18:00までにご来院ください。
【新潟】肛門外科・内科治療、いぼ痔や切れ痔に役立つコラム
- 【新潟】肛門が痒い原因とは?市販薬使用時の注意点や肛門外科受診の重要性
- 【新潟】肛門の痛みの原因・放置するリスク・肛門外科の診察内容
- 【新潟】肛門から出血を引き起こす疾患や肛門外科受診の目安について
- 【新潟】肛門内科の受診は恥ずかしい?配慮のポイントと早期受診のメリット
- 【新潟】肛門内科で対応する症状や診察の流れ・検査内容とは?
- 【新潟 肛門内科】便秘の特徴・生活習慣の見直しポイント・排便習慣の作り方
- 【新潟】いぼ痔の悪化を防ぐ!座り方と日常生活でできる予防法
- 【新潟】いぼ痔の進行段階や症状を悪化させるNG習慣とは?
- 【新潟】切れ痔の放置は危険信号!悪化・再発を防ぐための対処法
- 【新潟】切れ痔の悪化を防ぐには?排便習慣とトイレのコツ