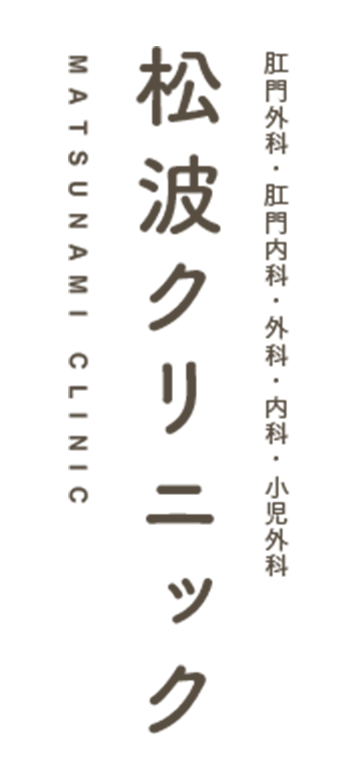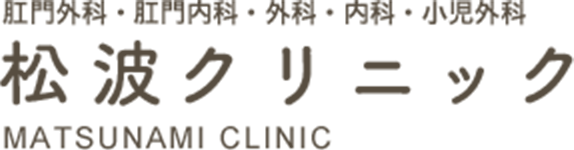【新潟】肛門内科で対応する症状や診察の流れ・検査内容とは?
【新潟】肛門内科で診療を行う症状とは?診察の流れや検査内容などをも解説
肛門の不調を感じても、「どこで診てもらえばいいのかわからない」「恥ずかしくて受診しづらい」と感じていませんか。そんなときに相談先となるのが肛門内科です。新潟周辺で肛門に関する悩みを解消したい方に向けて、肛門内科で診療を行う症状、診察の流れ、受診時のポイントについて解説いたします。
肛門内科で診てもらえる症状とは?受診が多いケースも紹介

肛門内科では、痔をはじめとする肛門の疾患全般を診療します。適切な診断と治療で、患者様の生活の質(QOL)向上をサポートします。
主な対象疾患
肛門内科では、さまざまな疾患の診療に対応しています。
いぼ痔(痔核)
いぼ痔は、肛門の血管がうっ血して腫れたもので、内痔核と外痔核に分けられます。内痔核は痛みが少ないものの、排便時に出血したり、肛門から脱出したり(脱肛)することがあります。外痔核は肛門の外側にでき、血栓ができると激しい痛みを伴います。生活習慣の改善や薬物療法、場合によっては手術が検討されます。
切れ痔(裂肛)
切れ痔は、硬い便の排出などで肛門の皮膚が切れてしまう状態です。排便時に鋭い痛みがあり、少量ですが出血を伴うこともあります。何度も繰り返すと慢性化し、肛門が狭くなる肛門狭窄を引き起こします。便秘の解消や緩下剤の使用、軟膏による治療が一般的です。
痔瘻(あな痔)
痔瘻は、肛門の直腸と皮膚の間にトンネルのような膿の管ができてしまう病気です。肛門周囲の腫れや痛み、発熱、膿の排出などの症状が現れます。自然治癒は難しく、手術による根本的な治療が必要です。
肛門周囲膿瘍
肛門周囲膿瘍は、肛門の周りに膿がたまる状態です。激しい痛みや腫れ、発熱を伴います。膿が排出されると一時的に楽になりますが、放置すると痔瘻へ進行します。切開して膿を出す処置が必要です。
直腸脱・直腸粘膜脱
直腸の一部または全体が肛門から飛び出してしまう状態です。排便時だけでなく、咳やくしゃみなどでも脱出することがあります。違和感や不快感を伴い、出血も見られます。症状が軽ければ保存的治療も可能ですが、進行すると手術が必要です。
肛門掻痒症
肛門周辺の強いかゆみが主な症状です。湿疹や皮膚炎を併発する場合もあります。原因は多岐にわたりますが、過剰な清潔さの追求、不十分な衛生状態、アレルギー、真菌感染などが挙げられます。適切な診断と治療が欠かせません。
肛門内科の受診が多いケース
肛門内科を受診される方の多くは、以下のような症状を抱えています。
排便時の出血
排便時の出血は、よく見られる症状であり、いぼ痔や切れ痔が代表的な原因です。トイレットペーパーに血が付着する程度から、便器が真っ赤になるほどの大量出血までさまざまです。痔以外の疾患が原因の場合もあるため、自己判断せず、診察を受けることが重要です。
肛門の痛み
痛みの種類、程度、持続時間に応じて疑われる疾患が異なります。排便時や排便後、あるいは日常的に肛門に痛みを感じる場合、いぼ痔、切れ痔、肛門周囲膿瘍などが疑われます。
肛門からの脱出・腫れ
排便時に肛門から何かが突出する、または肛門周辺に腫れを感じる場合、いぼ痔の脱出、直腸脱、肛門周囲膿瘍などが考えられます。脱出の程度や戻るかどうかなども診断の重要な手掛かりとなります。
肛門のかゆみ
持続する肛門のかゆみは、肛門掻痒症や皮膚炎の兆候かもしれません。不適切な清潔習慣や特定の食品、ストレスなども関与することがあります。
軽微な症状に思えても、放置することで悪化する懸念があります。早期に受診することで、適切な診断と治療を開始できます。また、生活習慣の見直しも重要です。
肛門内科の診察はどう進む?具体的な流れと検査内容

肛門内科を受診する際、「どんな診察をされるのだろう」「痛くないだろうか」といった不安を感じる方は少なくありません。事前に診察の流れや検査内容を知っておくことで、落ち着いて受診することができます。
初診時の問診と診察室での対応
問診
まず受付で問診票の記入を行います。現在の症状、既往歴、服用している薬、アレルギーの有無、生活習慣(排便習慣、食生活など)について記入します。これらの情報は正確な診断のために不可欠です。
その後、問診票の内容に基づいて、医師がさらに詳しく確認します。「排便時に出血がある」「排便後も痛みが続く」「肛門から何かが出ている感じがする」など、具体的にお伝えください。また、気になることや不安なことがあれば、遠慮なく質問してください。
診察室での準備と配慮
診察室では患者様のプライバシーを尊重し、タオルやガウンなどで患部以外を隠します。診察台への移動や体位の取り方についても、スタッフが丁寧に説明し、サポートします。横向きの「シムス位」、うつ伏せで膝を曲げる「砕石位」といった体位をとることが一般的です。リラックスできるよう、深呼吸などを促します。
診察の流れ
問診が終わると、いよいよ肛門の診察です
視診
医師が肛門周辺の皮膚の状態を目で確認します。いぼ痔の有無、切れ痔の場所、皮膚の炎症や腫れ、膿の有無などを確認します。赤み、腫れ、ただれなど、見た目でわかる症状を観察します。
触診(指診)
指を肛門に挿入し、直腸内を触って確認する検査です。直腸内のポリープや腫瘍、いぼ痔の有無や大きさ、硬さ、肛門括約筋の緊張具合、痛みの有無などを確認します。
肛門鏡検査
肛門鏡という筒状の器具を肛門に挿入し、肛門管の内部を直接観察する検査です。内痔核の状態、切れ痔の有無、粘膜の炎症などを詳細に確認できます。肛門鏡はさまざまなサイズがあり、患者様の状態に合わせて適切なものを選びます。多くの場合、痛みは少なく、短時間で終わります。
検査後の説明と治療方針の決定
診察や検査が終わると、医師から診断結果と病状について説明があります。病名、現在の症状の原因、今後の見通しなどについて、わかりやすく説明します。不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。
さらに、診断結果に基づいて、患者様に適した治療方針を提案します。治療法には、生活習慣の改善、薬物療法、日帰り手術、入院手術など、さまざまな選択肢があります。各治療法のメリットとデメリット、予想される効果、リスク、費用などを詳しく説明し、ご納得のうえで治療を進めていきます。
肛門内科の受診が不安な方へ!恥ずかしさを減らす準備と当日の注意点
肛門内科を受診する場合、いくつかの準備と受診時のポイントを押さえることで、スムーズに診察を受けることができます。
受診前にできること
受診前の準備として以下が挙げられます。
症状をメモする
いつから、どのような症状が、どの程度あるのかを具体的にメモしておきましょう。
- 排便時に鮮血が出る
- 痛みはないが、トイレットペーパーに少量の血液が付着する
- 肛門にイボのようなものができ、排便時に出てくるが、手で押し込むと戻る
- 肛門の周りがかゆい。特に夜にひどくなる
- 排便後、鋭い痛みが数時間続く
このような情報を準備しておくと、医師にも相談しやすくなります。出血の量や色、痛みの種類(ズキズキする、チクチクするなど)も重要な情報です。
既往歴と服用中の薬のリストアップ
これまでに罹患した病気、現在服用している薬(市販薬、サプリメントなども含む)をリストアップしておきましょう。特に、血液をサラサラにする薬(抗凝固剤など)を服用している場合は、必ず医師にお伝えください。アレルギーの有無も重要です。
受診時のポイント
肛門内科を受診する際に知っておきたいポイントをまとめました。
服装について
特に決まりはありませんが、着脱しやすい上下に分かれた服装がおすすめです。ワンピースよりも、Tシャツとズボンなどの組み合わせのほうが診察時に便利です。診察台に上がることを考慮し、締め付けが少なく、リラックスできる服を選ぶとよいでしょう。
痛みに不安がある場合
診察や処置で痛みが心配なときは、あらかじめ伝えておくと安心です。麻酔ゼリーを使ったり、器具の工夫によって負担を減らしたりと、痛みに配慮した方法を選べます。無理に我慢する必要はありません。
「恥ずかしい」「大したことではない」と感じている間に、症状が進行してしまうケースもあります。肛門内科は、そうした不安や疑問に対して丁寧な対応を行う診療科です。相談しやすい雰囲気があると、それだけで気持ちが楽になります。
新潟周辺で肛門内科を受診するなら松波クリニックへ
おしりの悩みを解決したいとお考えの際は、新潟の松波クリニックまでご相談ください。肛門外科・肛門内科の担当医として、患者様一人ひとりに合った診療を心がけております。肛門疾患の治療はもちろん、日常生活や排便習慣の改善サポートもお任せください。
【新潟】肛門外科・内科治療、いぼ痔や切れ痔に役立つコラム
- 【新潟】肛門が痒い原因とは?市販薬使用時の注意点や肛門外科受診の重要性
- 【新潟】肛門の痛みの原因・放置するリスク・肛門外科の診察内容
- 【新潟】肛門から出血を引き起こす疾患や肛門外科受診の目安について
- 【新潟】肛門内科の受診は恥ずかしい?配慮のポイントと早期受診のメリット
- 【新潟】肛門内科で対応する症状や診察の流れ・検査内容とは?
- 【新潟 肛門内科】便秘の特徴・生活習慣の見直しポイント・排便習慣の作り方
- 【新潟】いぼ痔の悪化を防ぐ!座り方と日常生活でできる予防法
- 【新潟】いぼ痔の進行段階や症状を悪化させるNG習慣とは?
- 【新潟】切れ痔の放置は危険信号!悪化・再発を防ぐための対処法
- 【新潟】切れ痔の悪化を防ぐには?排便習慣とトイレのコツ