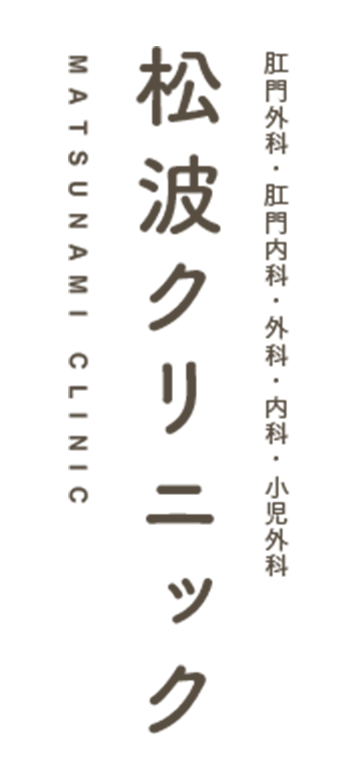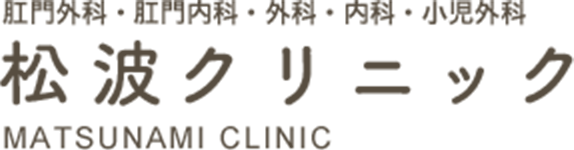【新潟 診療】切れ痔で肛門外科を受診するタイミングや問診で聞かれること
【新潟 診療】切れ痔で肛門外科を受診するタイミングとは?問診で聞かれることや再発を防ぐための生活習慣の見直しポイント
切れ痔は、排便時の刺激などによって肛門の皮膚が切れてしまう状態を指します。鋭い痛みや少量の出血を伴うのが特徴です。硬い便を無理に出そうとしたときや、強いいきみが続いたとき、下痢による刺激で生じることもあります。一度できると排便のたびに傷が開き、治りにくくなることもあるため、繰り返すようなら放置せずに対処することが重要です。
こちらでは、肛門外科を受診するタイミング、問診で聞かれること・診察の流れ、生活習慣を見直すポイントなどをご紹介いたします。新潟周辺でおしりのトラブルに関する診療を受けたい方も参考にしていただければ幸いです。
こんなときは肛門外科へ!受診のタイミング

軽い切れ痔であれば自然に回復することもありますが、症状によっては治療が必要になるケースもあります。切れ痔の症状で、肛門外科を受診したいタイミングは以下のとおりです。
出血が続く、または量が多い
排便のたびに鮮血が出る場合、まず考えられるのは切れ痔ですが、大腸ポリープや直腸がんなど、別の病気が潜んでいることもあります。血の色や量、出血のタイミングをよく観察しておくと診察時の参考になります。
強い痛みや腫れがある
切れ痔では鋭い痛みが出るのが特徴です。排便後も痛みが長引いたり、腫れて座るのがつらい場合、症状が進行しているサインかもしれません。ズキズキする、突き刺すような痛みがあるなど、痛みの性質を伝えると診断がスムーズです。
市販薬で改善しない
市販薬で一時的に症状が和らいでも、数日してまた悪化する…という状態を繰り返すなら、切れ痔が慢性化し始めている可能性があります。傷が深くなっていたり、潰瘍のようになっていたりすると、自然治癒は難しいです。
発熱や膿が出る
肛門周囲が熱を持ったり、押すと膿がにじむような場合は、細菌感染による肛門周囲膿瘍が疑われます。この状態を放置すると、膿が溜まりきって膿瘍が破裂したり、あな痔(痔ろう)に移行したりすることもあるため、早めの対処が必要です。
繰り返している、または長く続いている
治ったと思ってもすぐ再発する、あるいは何週間も同じ状態が続いている場合、便の性状や排便習慣、肛門周囲の環境に慢性的な問題があることが考えられます。きちんと診察を受け、体質や生活習慣に合った対処法を見つけることが、再発予防につながります。
切れ痔だと思っていたら、実は他の肛門疾患や消化器系の病気が隠れていたというケースも多いです。「いつもと違う」と感じるときは、肛門外科の受診をご検討ください。
問診で聞かれること・診察の流れ

診察ではいきなり患部を調べることはなく、まず問診から始まります。自分が感じている症状や、日常の排便の様子などについて話すことが中心です。恥ずかしさを感じるかもしれませんが、スムーズな診断と治療のために大切なステップです。
問診の主な内容
問診では、医師が症状の原因を正しく判断するために、さまざまな情報を確認します。
症状が出た時期と続いている期間
「いつから痛みや出血があるか」は、診断の出発点になります。突然始まったのか、何度も繰り返しているのかといった情報は、急性か慢性かを判断する手がかりになります。
痛みや出血の程度・頻度
排便中にズキッと痛むのか、排便後も鈍痛が続くのかなど、痛みの特徴を伺います。出血については「トイレットペーパーにつく程度」「便器が赤くなる」といった状況から、症状に対する理解を深めます。
普段の排便習慣と便の状態
便秘や下痢を繰り返していると、肛門に負担がかかりやすくなります。排便の頻度、便の硬さ、我慢することが多いかどうかなど、日頃の排便状況も重要な情報です。
これまでの病歴や体の変化
過去に痔を患ったことがあるか、肛門の手術歴があるか、妊娠・出産の経験があるかなども確認します。これらは切れ痔の再発や慢性化にかかわる情報です。
生活習慣や服薬状況
食生活や運動習慣、仕事中の姿勢など、日常の過ごし方も確認します。また、服用している薬によっては便が硬くなったり、排便に影響が出ることもあります。薬の名前が不明な場合でも、便通の変化との関連に心当たりがあればお伝えください。
このように、問診では症状そのものだけでなく、背景となる生活習慣や体の状態についても幅広く確認します。気になることがあれば遠慮せずに伝えることが、適切な治療につながります。
診察の流れ
問診後、肛門の状態を調べます。診察では、ベッドの上で横向きになり、膝を胸に引き寄せる姿勢(側臥位)をとるのが一般的です。視診や触診・指診で、肛門の周りの皮膚の状態を確認します。肛門鏡による検査で、肛門の内側と直腸の診察も行います。診察・検査の後は、現在の症状や患者様の状態なども踏まえて、治療法をご説明します。
疑問点や不明点を解消し、患者様が納得したうえで治療を進めていきます。気になることがあれば、些細なことでも質問しましょう。
切れ痔をくり返さないために!生活習慣の見直し
切れ痔は、生活習慣と密接なかかわりがあります。再発を予防するためには、日々の生活習慣を見直すことも重要なポイントです。
排便のリズムを整える
毎朝同じ時間にトイレへ行く習慣をつけると、排便のリズムが整ってきます。また、排便時は無理にいきまず、できるだけ短時間で済ませるよう意識しましょう。特に、排便中にスマートフォンを操作していると、気づかないうちにトイレにいる時間が長くなり、肛門に余計な力がかかってしまうため、注意が必要です。
食生活と運動習慣
便秘や下痢は切れ痔の大きな原因です。特に硬い便は肛門に強い負担がかかるため、適度な水分と食物繊維を意識して取り入れましょう。例えば、起床時にコップ1杯の水や白湯を飲むと腸の動きが促進され、スムーズな排便が期待できます。食物繊維は野菜や果物、海藻、豆類などからバランス良く摂取することがポイントです。ウォーキングやストレッチなど、軽めの運動も腸の活動や血流の改善に役立ちます。
肛門まわりのケア
排便後はウォシュレットやぬるま湯でやさしく洗い、ゴシゴシこすらずやわらかいトイレットペーパーで押さえるように拭くことがコツです。刺激の強い石けんの使用や粗い素材の下着は避け、できるだけ肌にやさしいものを選びましょう。
冷えとストレスへの対処
体が冷えると血行が悪くなり、肛門周囲にも影響を与えます。冷房の効いた室内ではブランケットやカイロを活用するなど、冷え対策をしっかり行いましょう。また、ストレスがたまると自律神経が乱れ、腸の動きにも影響が出やすくなります。睡眠や休養の時間を確保し、自分に合ったリラックス法を見つけることが大切です。
切れ痔をはじめ、痔は年齢や性別を問わず、誰にでも起こる可能性があります。体からのサインに早めに気づき、適切に対応することがつらい症状の改善につながります。
痔の悩みを相談するなら新潟の松波クリニックへ
松波クリニックは新潟市中央区を拠点に、おしりの悩み・心配事を解決するためのサポートを行います。通院治療を主体に、親切丁寧な診療を心がけております。日帰り手術にも対応可能です。気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
【新潟】肛門外科と肛門内科、いぼ痔・切れ痔に役立つコラム
- 【新潟】日帰り手術対象の肛門疾患や肛門外科受診のサインとは?
- 【新潟 肛門外科】女性がなりやすい肛門疾患やクリニック選びのポイント
- 【新潟】土曜日診療に対応する肛門外科の利用ガイド
- 【新潟 肛門内科】規則正しい排便のポイントや排便トラブルの原因とは?
- 【新潟 肛門内科】受診のきっかけになる症状・診察の流れ・初診時の持ち物
- 【新潟 肛門内科】夜間診療のメリット・注意点や応急処置の方法は?
- 【新潟】痔は早期発見・治療を!いぼ痔の進行段階や悪化する原因とは?
- 【新潟】女性に多いいぼ痔・切れ痔の特徴や痔になりやすい理由とは?
- 【新潟】切れ痔の治療前に確認!主な原因・症状や放置するリスクとは?
- 【新潟 診療】切れ痔で肛門外科を受診するタイミングや問診で聞かれること