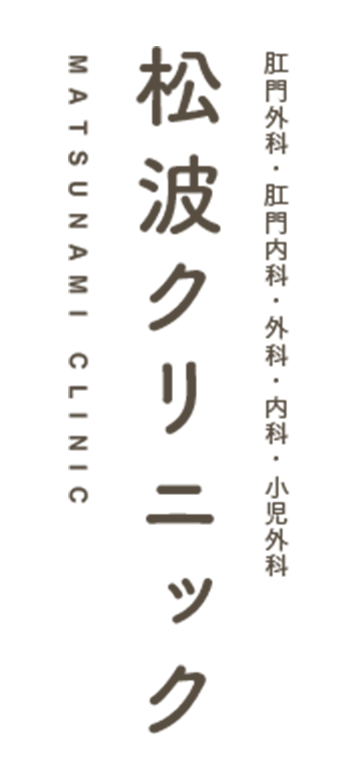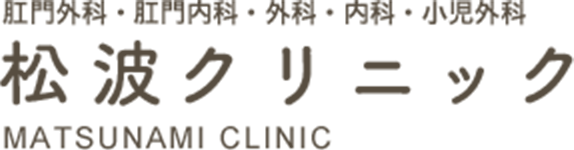【新潟】お通じが良くなる!飲み物&食べ物について
お通じが良くなる飲み物&食べ物について新潟の肛門科医が解説!
日々のお通じは快適な生活を送るうえで欠かせません。お酒や料理を楽しむ際は、水分補給を十分に行い、食物繊維やオリゴ糖の多い食材を意識的に摂取しましょう。お通じのお悩みは新潟の松波クリニックへご相談ください。
お酒と便秘の関係とお酒を楽しむ際のポイント

お酒と便秘の関係
お酒が便秘になりやすい理由
お酒は利尿作用があり、体内の水分を排出させるため、便が硬くなりやすくなります。また、お酒には発酵過程で生まれるプリン体が含まれているものも多く、プリン体はたんぱく質の一種で便の量を減らす作用があります。
さらに、お酒には下剤成分は入っていないため、腸の動きを促す働きがありません。このため、お酒を飲むと便通が悪化する傾向にあります。
加えて、お酒には炭水化物やたんぱく質が含まれているものの、食物繊維は含まれていません。食物繊維が不足すると、便の量が減り便秘になりやすくなるのです。
お酒を飲む際は、水分補給を十分に行う、食物繊維の多い食べ物を一緒に摂取するなど、便秘対策が重要になります。
お酒の種類による違い
お酒の種類によって、体への影響に違いがあります。例えば、ビールなどのアルコール度数の低い発泡酒は、利尿作用が強く、水分を排出しやすくなります。一方、ワインなどのアルコール度数の高い酒類は腸の蠕動運動を抑制する傾向があり、便秘になりやすいのが特徴です。
| お酒の種類 | 利尿作用 | 腸への影響 |
|---|---|---|
| ビール | 強い | 抑制的ではない |
| ワイン | 弱い | 抑制的 |
| 焼酎 | 弱い | 抑制的 |
このように、お酒の種類によって便秘や下痢の起こりやすさが異なります。お通じを良くするためには、飲み物の選び方が重要です。
お酒を飲む際の食生活のポイント
お酒を飲む際の食生活では、以下の3つのポイントに気をつけることが大切です。
バランスの良い食事
野菜や穀物などからたっぷりの食物繊維を摂り、発酵食品からは腸内環境を整える乳酸菌なども補給しましょう。脂肪の摂りすぎにも注意が必要です。
個人に合わせた対策
年齢や体質、生活習慣によって便秘のリスクは変わります。ストレスが溜まりやすい人は食物繊維を意識的に取り入れる、高齢者は水分補給に気をつけるなど、個人に合わせた対策が重要です。
生活リズムの大切さ
お酒を飲んだ翌日は二日酔いで体調を崩しがちです。規則正しい生活リズムを守り、適度な運動を心がけることで便秘リスクを下げられます。
お通じを良くする!飲み物と食べ物に関する注意点

お通じを良くする飲み物について
水分補給が大切
お酒を飲む際は、水分補給を心がけましょう。お酒は利尿作用があり、体内の水分バランスを崩しやすくなります。このため、お酒を飲む前や飲んでいる間、そして翌日は、こまめに水分を摂ることが大切です。
水分を十分に摂らないと、以下のような不調が起こる可能性があります。
- 便秘
- 頭痛
- めまい
- イライラ、ストレス
- 疲労感
- 肌荒れ
一方、適切に水分を摂ることで、以下のようなメリットが期待できます。
- 血液のドロドロを解消し、脂質を排出
- 生活習慣病の改善(糖尿病、高血圧など)
- ボケ防止、脳の活性化
- 胃腸の働きが活性化
- 疲れやストレスの解消
- 冷え防止
- 肥満の改善
- 美肌効果
- 免疫力アップ
お酒の翌日は特に水分が不足しがちですので、こまめな水分補給に気をつけましょう。
乳酸菌飲料の効果
乳酸菌飲料は、発酵食品と同様に乳酸菌を多く含む飲料です。乳酸菌飲料には、腸内環境の改善・整腸作用・ビタミン産生などの効果が期待できます。
その他の発酵飲料
発酵飲料の中には、乳酸菌飲料以外にもお通じを良くするものがあります。例えば、紅茶キノコや昆布茶、ぬか漬けの漬け汁などが挙げられます。これらの飲み物には食物繊維が豊富に含まれており、腸内環境を整える働きがあります。
特に、ぬか漬け汁には、発酵によってつくられた乳酸菌が含まれているため、腸内環境を改善する効果が期待できます。生きた菌を取り入れることで、お酒を飲んでも腸内環境を整えられるのが発酵飲料の利点です。
お通じを良くする食べ物について
食物繊維の役割
食物繊維は、便秘の予防に大きな役割を果たします。消化管内で水分を保持する作用があり、便の量を増やすことができます。
さらに、食物繊維は善玉菌のエサとなるため、腸内環境を整えます。ビフィズス菌や乳酸菌などの腸内細菌を増やし、お通じを改善する効果があります。
加えて、食物繊維には以下のような働きもあります。
- 血糖値の上昇の抑制
- 血中コレステロール値の低下
- がんや糖尿病など生活習慣病発症リスクの低減
1日の目標摂取量は男性21g以上、女性18g以上とされています。現在の日本人の平均摂取量は14g前後と不足気味なので、積極的な摂取が推奨されます。
オリゴ糖の働き
オリゴ糖は、消化・吸収されずに大腸に届きます。そこで善玉菌であるビフィズス菌の「エサ」となり、ビフィズス菌を増やします。
ビフィズス菌が増えると、以下のような働きがあります。
- 酢酸やプロピオン酸などの有機酸を生成し、腸内環境を整える
- 弱酸性になり悪玉菌の活動を抑制する
- 腸の蠕動運動が活発になり、便秘が改善する
- ミネラル(カルシウムなど)の吸収を促進する
このように、オリゴ糖はビフィズス菌を増やすことで「整腸作用」と「ミネラル吸収促進作用」をもたらします。
生活習慣・排便習慣の改善を指導!便秘や便秘による肛門疾患にお悩みなら
お酒や料理を楽しむ際の便秘対策は重要です。お酒や食事の種類や量によっても便秘のリスクは変わります。また、就寝時間や運動量など生活リズムの乱れが便秘を引き起こすことも珍しくありません。お酒や料理を楽しむ際は、水分補給を十分に行い、食物繊維やオリゴ糖の多い食材を意識的に摂取することをおすすめします。
新潟の松波クリニックは、患者様にとって最適な治療を追求し、快適な環境を提供する肛門科です。肛門外科・肛門内科の担当医として、便秘や便秘による肛門疾患などおしりに悩みをお持ちの方に専門的な治療を行っております。日常生活や排便習慣の改善に重点を置いています。便秘や肛門疾患にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。