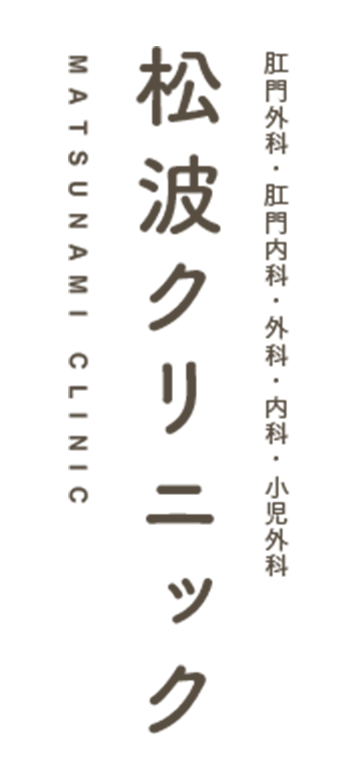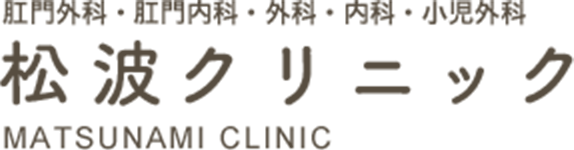【新潟】便秘・痔の薬の上手な使い方!医師が解説する副作用への対処法
新潟の肛門科医が解説!便秘・痔の薬の上手な使い方と副作用への対処法
便秘薬には非刺激性下剤・刺激性下剤、痔の薬には注入軟膏や坐剤など様々な種類があります。便秘や痔の状態になった際は、症状に合った薬剤を選ぶことが大切です。便秘や痔にお悩みの方は、新潟の松波クリニックまでご相談ください。
便秘・痔の薬の選び方と使い方

便秘薬の種類
便秘薬には、大きく分けて「非刺激性下剤」と「刺激性下剤」の2種類があります。
非刺激性下剤
- 塩類下剤:便に水分を集め、便を柔らかくする
- 浸潤性下剤:界面活性作用により、便の水分を浸潤させて便を柔らかくする
- 膨張性下剤:服用した水や腸管内の水分を吸収して便を大きくし、排便を促す
刺激性下剤
- センノシド系薬剤
腸管運動を刺激して排便を促す便秘薬です。腸管の動きを活発化させますが、長期使用すると腸に負担をかけます。
便秘薬の選び方と上手な使い方
非刺激性下剤は、症状に応じて自分に合った量を調節することが可能です。軟便や下痢にならないよう、便通の状況を見ながら服用量を細かく調整してください。
また、刺激性下剤は大腸や小腸に直接作用するため、長期使用するとクセがついてしまい、効果が薄れてくる可能性があります。なお、即効性が高いため、すぐにトイレに行ける状態で使用してください。
年齢や体調、症状の程度に合わせて、医師に相談しながら適切な便秘薬を選ぶことが重要です。
痔の薬の選び方
痔の薬には、注入軟膏・坐剤・軟膏・内服薬などさまざまな種類があります。
痔の症状や痔の種類(内側のいぼ痔、外側のいぼ痔、切れ痔など)に応じて、適切な剤形を選ぶことが重要です。
また、ステロイド配合の有無で効果が異なります。ステロイド配合製剤は強い消炎・鎮痛作用がありますが、長期連用は避けるべきです。一方、ステロイド非配合製剤は症状改善に時間がかかる場合があります。症状に合わせて使い分けてみてください。
痔の薬の上手な使い方
注入軟膏の使い方
- 1.キャップをはずし、軟膏をノズル先端部より少し出します。
- 2.ノズル部分を肛門内に挿入します。
- 3.ボディ部分を押してゆっくり注入し、押したままで引き抜きます。
※1回量は全量を使い切り、容器全体は入れないでください。
軟膏の使い方
キャップをはずし、清潔な指に患部を覆う量の軟膏を取り、患部に塗布するか、ガーゼなどにのばして患部に貼付します。
軟膏が硬くて押し出しにくい場合は、容器を手で握ってあたためると軟らかくなります。
便秘薬による副作用への対処法

下痢や軟便になった場合の対応
便秘薬の初回服用時は、薬の効果が強く出る場合があります。その日だけ下痢や軟便になっても、次の日から便質が改善されることがあります。
下痢や軟便が続く場合は、便秘薬の量を減らすことで対処できます。症状に合わせて適量を調節することが重要です。
上記の対応をしても改善が見られない場合は、医師に相談しましょう。医師の指示に従って用法・用量を変更するなどの対応が必要です。
便質が改善されない場合の対応
一定期間、生活習慣の改善や便秘薬の服用などの対処を行っても便質に改善が見られない場合は、医師に相談することが重要です。便秘が長期化すると、以下のような症状が現れる可能性があります。
- 腹痛や腹部膨満感
- 食欲不振
- 吐き気
- 頭痛
これらの症状が現れた場合は、大腸がんや炎症性腸疾患、甲状腺機能低下症、パーキンソン病など、便秘の原因が何か別の病気にあるおそれがあります。
医師は問診や血液検査、画像検査などを行い、原因を特定します。そのうえで適切な治療を行うことで、便秘を改善させることができます。
自己判断で放置せず、早期に医師に相談しましょう。
症状に合った治療法・薬剤をご提案!新潟で辛い便秘や痔にお悩みなら
便秘薬には非刺激性下剤・刺激性下剤、痔の薬には注入軟膏、坐剤、軟膏、内服薬など様々な種類があります。便秘や痔の状態になったときは、薬の選び方と使い方をしっかりと理解し、症状に合った薬剤を選ぶことが大切です。
生活習慣の改善も便秘や痔の予防に欠かせません。食生活や運動に気をつけ、症状が改善するまでは便秘や痔の悪化を防ぐ生活を心がけましょう。
新潟の松波クリニックでは、肛門外科・肛門内科の担当医として、おしりに悩みをお持ちの方に専門的な治療を行っております。辛い便秘や痔の症状にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。